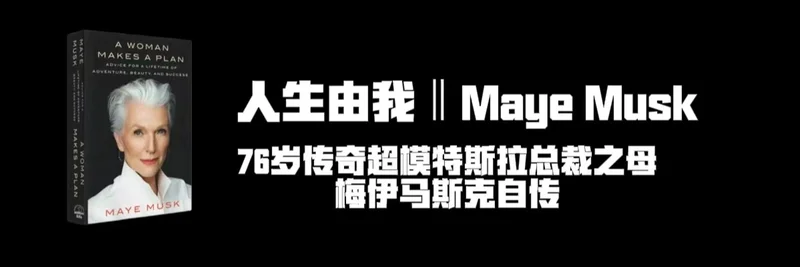暗号通貨の早い流れの中で、物語は移り変わるが、ミームトークンの進化ほど想像力をかき立てるものは少ない。最近、Defiance Capitalの投資家Kyleが示した思考を促すツイートがコミュニティで議論を呼んでいる。自身の以前の投稿を引用して—"first came ICM next came PMF"—彼は「ユーティリティズ・シーズン」を期待していると表明した。上昇相場で全ての船が上がるのではなく、個別のプロダクトが実績のある分野で構築され、広範なラリーから離れて評価されることを望んでいるというわけだ。
これを分解してみよう。ICM、つまり Internet Capital Markets は、スタートアップやプロダクト、あるいはミームですら、アイデアがトークン化されブロックチェーン上で直接資金調達される新たな潮流を指す。プラットフォームとしては pump.fun や Solana上の Believe のようなサービスがこれを可能にしており、誰でも最低限の障壁でトークンを立ち上げられる。クラウドファンディングとミームコインが合わさったようなもので、X(旧Twitter)にアイデアを投稿し、ローンチャーをタグ付けすれば、瞬時にそのコンセプトが取引可能な資産になる。従来のVCやピッチデッキを経ずにコミュニティの即時支援が得られることで、資金調達の民主化が進んでいる。
ICMに続くのがPMF、つまり Product-Market Fit だ。これはトークンやプロジェクトがユーザーに受け入れられ、本当の需要と持続可能性を示す段階を指す。ミームトークンの文脈では、単に楽しいアイデアが、コミュニティが拡大し続けたり、価値を付与する機能が加わったりして、定着力を持つものに変わる瞬間だ。
Kyleが期待するユーティリティ主導のシーズンは、この流れの延長線上にある。ユーティリティとは実際のユースケースのことで、DeFiの統合、ゲームのメカニクス、あるいは現実世界での応用など、投機を超えてトークンに目的を与えるものを指す。現在の市場では、すべての船が潮に乗って上がるわけではない。堅牢な基盤とトラクションを持つプロジェクトだけが生き残り、成長するだろう。これは、ICMを通じて立ち上がったプロジェクトがユーティリティを備えた存在へと成熟する兆候かもしれない。
ブロックチェーン実務者にとって、この変化は重要な教訓を含んでいる。ミームトークンは単なるジョークではなく、より広範なイノベーションへの入口になり得る。AI支援のコンテンツ生成や分散型ショッピングのように、実績のあるバーティカルに注力することで、構築者は持続的な価値を生み出せる。パンプアンドダンプのサイクルを越えて、持続可能な成長を志向する呼びかけだ。
Kyleのツイートへの返信も同様の声を反映している。あるユーザーは広範なアプローチよりニッチ市場を称賛し、別のユーザーは本物のプロダクトに報われる時だと同意した。PM(おそらくProduct Management)への言及すらあり、この荒野での構造化された開発の必要性が強調されている。
文化、資本、コミュニティを融合させ続けるミームトークンの世界では、ICMからPMFへの移行に注目することで次の大きな機会を見つけられるかもしれない。degenトレーダーであれ真剣なビルダーであれ、この物語が教えてくれるのは一つ:暗号の世界では、トラクションがハイプに常に勝るということだ。