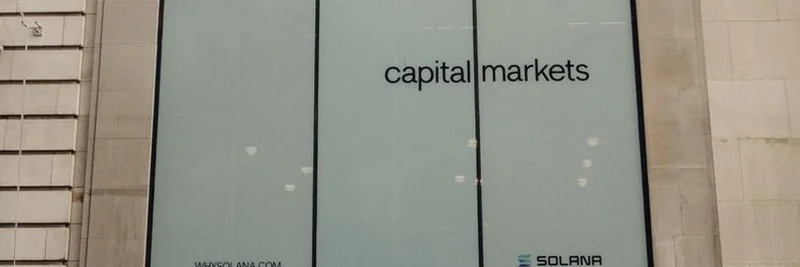皆さん、こんにちは、クリプト好きの皆さん!ブロックチェーンの最新動向を追っているなら、独自のトークノミクスで話題を呼んでいる InterLink に目を向けたことがあるはずです。最近、BSC News が InterLink のデュアルトークンモデルについて詳しい分析を公開しており、本当に目的に合った設計なのかを問いかけています。CoinDesk の編集デスクで暗号界の荒波を見てきて、現在は Meme Insider でミームトークンなどを掘り下げている私としては、これを分かりやすく噛み砕いてお伝えするのが楽しいだろうと思いました。InterLink が何を目指しているのか、この仕組みが次の大きな一手になり得るのか、それとも DeFi の中のもう一つの実験に終わるのか、見ていきましょう。
まず、InterLink の何が注目されているのか?このプロジェクト(X 上では @inter_link)は「人間中心(human-centric)」のネットワーク構築を標榜しています。つまり、単なる技術やボットではなく実際の人々にフォーカスするということです。彼らのトークノミクスは 2025 年 6 月中旬のホワイトペーパー更新で刷新され、デュアルトークン体制を導入しました:$LINKS(ドキュメントによっては $ITL と表記)と $INTL(または $ITLG)。一言で言えば、価値貯蔵と安定性を担うものと、日常的なユーティリティとコミュニティを活性化するもの、というビットコインとイーサリアムを合わせたような役割分担です。
まず $LINKS から。これは「戦略的リザーブ資産」と位置付けられ、InterLink Foundation によって管理されます。対象はベンチャーキャピタルや機関投資家のような大口プレイヤーです。なぜかというと、SEC のガイドラインに沿う形でセキュリティトークン扱いを想定するなど、規制面での適合を図れる可能性があるからです。総供給量は 100 億トークンで上限が設けられ、希少性を保ちます。そのうち半分の 50 億は $INTL 保有者に直接配分され、残りの半分は機関向け成長支援やエコシステムの安定化に充てられます。ステーキング好きには朗報で、このトークンをロックすることで「Human Layer」へのアクセス権が得られます。これは検証済みユーザーによる信頼できる相互作用のためのネットワーク層を指します。
次に $INTL。こちらはアクティブな参加を促すトークンです。驚くべきことに総供給量は 1,000 億トークンと桁が大きいですが、市場に無差別に放出されるわけではありません。80% は「Human Node miners」に割り当てられており、これらは紹介や身元確認などを通じて貢献する実在の人間に対するリワードです。残りの 20% はインセンティブに使われます。$INTL はガバナンスのための DAO を動かし、ローンチパッドへの早期アクセス権を与え、ゲームやサービスといったエコシステム内のミニアプリの標準通貨になります。さらに $INTL を保有していると $LINKS を獲得できる機会もありますが、逆方向の変換はできません。供給が 1,000 億に達した時点で、追加発行するか否かは DAO の投票で決められます。
マイニングの仕組みも面白く、特に初期段階で普及をブートストラップするのに適しています。これは「proof of personhood」——一人一ノード、一人一回のリワード機会——に紐づいており、ビットコインのようなハードウェア重視のマイニングとは対照的に包括的です。ボット対策としては ID 検証を取り入れ、ダンプ防止やインフレ抑制のためにベスティングを伴うロック機構も備えています。持続可能性が重視されており、初期参加者と新規参加者の報酬バランスを調整する設計になっています。
ただし InterLink は単なる理論にとどまりません。実世界での影響も見据えています。世界には 14 億人以上の銀行口座を持たない人々がいる(2021 年の World Bank データ)ため、$INTL を用いればシンプルなスマホの顔認証でピアツーピア決済が可能になるかもしれません。例えば NGO が危機地域の検証済み個人に直接支援を送ったり、WHO や UNICEF のような組織がマイクログラントを配布したりするユースケースが想像できます。Google や Meta のようなテック企業が AI トレーニング用のデータ提供に対してユーザーに支払う手段として使う可能性も(倫理的な扱いが前提ですが)あります。
どんな暗号プロジェクトにも長所と落とし穴があります。長所としては、真の人間の関与を報いる点、参入障壁が低い点、金融包摂や人道支援アプリへの大きなポテンシャルが挙げられます。DAO を軸にしたコミュニティ主導の動きは、うまくいけばバイラルに、ミーム的に成長する可能性を秘めています。一方で短所としては、採用が全てです——目標の 10 億ユーザーに到達できなければ勢いを失うかもしれません。セキュリティトークンの扱いを巡る規制リスクや、マイニング/ガバナンスのメカニクスが実社会で十分に機能するかどうかも試されます。
総じて、InterLink のデュアルトークン経済は安定性とユーティリティをうまく組み合わせた賢い設計に見えます。暗号を日常生活と橋渡しすることを目指すプロジェクトにとっては相性が良さそうです。コミュニティ志向の側面から「実はミームトークンなんじゃないか?」という見方もできますし、本気の DeFi プレイヤーとして台頭する可能性もあります。注目に値するプロジェクトだと言えるでしょう。興味がある方は BSC News の全文や @inter_link の更新をチェックしてみてください。皆さんはこの人間中心のムードに対して強気ですか?コメントで教えてください!