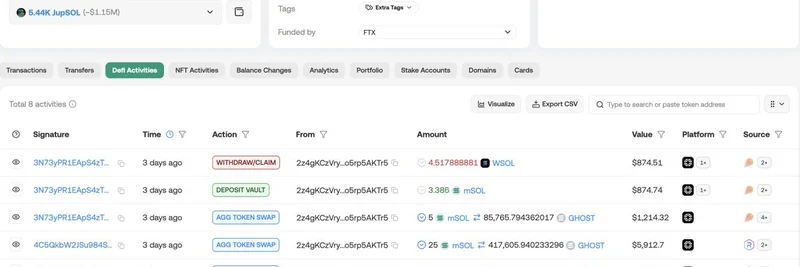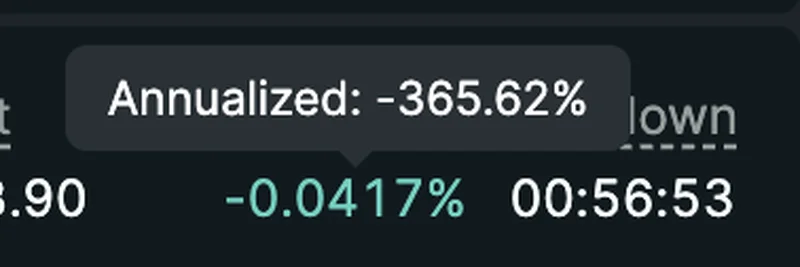BSCNewsがInterlinkのトークノミクスをツイートで公開して以来、暗号界は話題で持ちきりです。ミームトークンに興味がある人も、プロジェクトの経済設計に興味がある人も、一見の価値があります。Interlinkは典型的なポンプ・アンド・ダンプ系のミームではなく、「人間」を中心に据えたネットワークを構築しており、そのための巧妙なデュアルトークン設計を採用しています。
簡単に分解してみましょう。Interlinkは2種類のトークンを使っています:$ITL と $ITLG。$ITLは「大局」を担うトークンのようなもので、プロジェクトの財団が管理するリザーブファンドのイメージです。一方で $ITLG は一般ユーザーが関与し、報酬を得て運営に参加するためのトークンです。
まず基本から。$ITL の総供給量は固定で100億トークンです。その半分は $ITLG 保有者に割り当てられ、残りの半分はエコシステムの安定化を支える機関や大口プレイヤー向けに配分されます。このトークンは staking に重要で、要するにロックすることで Interlink の「Human Layer」へのアクセス権を得られます。Human Layer は検証された実在のユーザーのネットワークを指す言葉で、ボットは排除されます。パートナーやInterlink上でプロトコルを構築する場合、$ITL をステーキングすることで信頼できるユーザーベースにアクセスできます。
対照的に $ITLG は一般ユーザー向けのトークンです。供給量ははるかに多く、1000億トークン。うち80%は "Human Node miners" に割り当てられます。これらは本人確認や友人の紹介などを行うことでトークンを獲得する検証済みユーザーです。いわばマイニングのような仕組みですが、専用ハードウェアは不要で「実在の人間であることを証明する」ことに基づいて報酬が与えられます。残りの20%はコミュニティ成長のためのインセンティブに充てられます。
$ITLG の面白い点はそのユーティリティです。DAOでの投票に使え、これはコミュニティ主導の意思決定機構を意味します。例えば供給上限に達した後に追加でトークンをミントすべきかどうかといった重要な決定に関与できます。さらに新規プロジェクト向けの launchpads への早期アクセス権を与えたり、プラットフォーム上のミニアプリ(ゲームや各種サービス)の通貨としても機能します。
Interlink のモデルは大量のユーザーオンボーディングを想定しており、目標は10億人の検証済みユーザーです。現実世界での応用を考えると非常に大きな数字です。例えば銀行口座を持たない人々同士のピアツーピア決済を可能にしたり、AI企業と倫理的にデータを共有して報酬を得るといったユースケースが想像できます。公平性を保つために vesting スケジュールが設けられており、獲得した一部のトークンは一定期間ロックされ、急な売却(ダンプ)を防ぎバランスを維持します。
バーン(burning)メカニズムについての言及はありませんが、検証と動的な報酬設計によりインフレを抑制する工夫が見られます。早期参加者には優遇がありますが、新規参入者が置き去りにされないような構造になっている点も特徴です。このアンチボット設計により、本物の参加者だけが利益を享受できるようになっており、スキャムが氾濫する分野においては清涼剤のように感じられます。
ミームトークンやユーティリティ志向のプロジェクトを追っているなら、Interlink のトークノミクスは安全性とコミュニティパワーを組み合わせて持続可能な仕組みを作る一例を示しています。詳しくは元記事(BSC News)を参照するか、最新情報はInterlinkのTwitterをチェックしてください。もしかすると、ブロックチェーンをより「人間に優しい」ものにする次の大きな動きかもしれません。