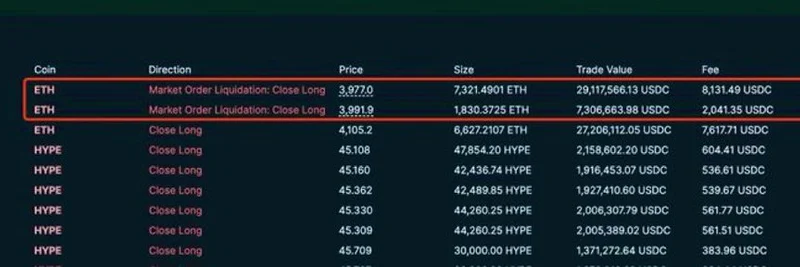BSCNewsが最近投下したツイートが仮想通貨界隈で話題になっています:これはJanctionのコアアーキテクチャに関する詳細な解説です。ブロックチェーンとAIに関心があるなら、リソース不足やプライバシーといった現実的な課題に対処するためにプロジェクトがどう進化しているかを示す、注目すべきアップデートです。彼らの投稿にある詳細をもとに、わかりやすく整理してみます。
Janctionとは何で、どこから来たのか?
Janctionは単なるブロックチェーンプロジェクトではなく、AI向けに特化したLayer2ソリューションです。分散型技術とAIが要求する大規模な処理能力の橋渡しをするイメージです。2023年に東京のJasmyLab Inc.を通じてJasmyコミュニティからインキュベーションとして始まりました。JasmyはIoTデータの分散化に注力しており、Janctionはその基盤の上に構築されています。
時間を進めると、2025年2月にJanctionはCogitent Ventures、DWF Labs、Waterdrip Capitalといった有力投資家からのシード資金を獲得しました。テストネットはOptimism OP Stack上でローンチされており、つまりEVM-compatibleで、メインチェーンを詰まらせることなくAIタスクをスケールするのに適しています。
Janctionの中核:主要アーキテクチャ要素
Janctionの中核は、決済(settlement)レイヤー、GPUプーリング、そしてマーケットプレイスを統合し、AIサービスをよりアクセスしやすく効率的にする点にあります。以下は各要素の位置づけです。
Blockchain Layer:決済とデータの扱い
ここが全てを取りまとめるバックボーンです。データ保存、トランザクション、報酬の管理を担います。データはブラウザ拡張やオンチェーンのアップロード経由で流入します—ユーザーはChatGPTのクエリやソーシャルメディアの情報などを、トランザクションに署名した上で共有できます。
動作の要はProof of Contributionというコンセンサスアルゴリズムです。これが入力を検証し、各参加者が貢献度に応じて公平に報酬を受け取れるようにします。全トランザクションはData Availability (DA)レイヤーに記録され、透明性が担保されます。ブラックボックスは存在せず、検証可能な貢献が重視されています。
Distributed Resource Pooling:GPUをより賢く使う
GPUはAIのコア資源ですが、2024〜2025年の不足で入手が難しくなりました。Janctionは遊休GPUを集約して標準仕様の仮想GPU(vGPUs)に変換することでこれを解決します。組織化にはマイクロサービス構成の中でVxLan技術を用いています。
割り当てはスマートなルーティングとスケジューリングアルゴリズムで行われ、価格決定はPVCGメカニズムで管理されます。AIサービスはRESTful APIsを通じて通信し、バックエンドは簡単なサービスアクセスを提供します。このDePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network)的アプローチはリソースをトークン化し、誰でも寄与して報酬を得られる仕組みを作ります。中央集権的なゲートキーパーは不要です。
GPU Marketplace:全てが結びつく場所
ここがユーザー、ノード、サービスのハブとなります。ユーザー情報の追跡、ノードの監視、評判システムの運用を行い、不正行為の排除や誠実な参加を促します。
主要な役割:
- GPUプロバイダー:ハードウェアを供給し、報酬を得る。
- Aggregators:リソースプールを構築・管理し、オンチェーンのステーキングで選出される。
- ユーザー:必要に応じてGPUを利用する。
誰でもJanction Blockchainにステークしてノードになることができ、収益はステークに基づいて分配されます。計算資源を取引する、公平で構造化された方法です。
ポテンシャルを高めるパートナーシップ
Janctionは孤立して動いているわけではありません。DMC DAOとは2000万のDJの音源ライブラリからのコンテンツを組み込み、視聴者に報酬を与えクリエイター経済を活性化する連携を行っており、これは2025年9月に再発表されました。さらに、分散型クラウドゲーム向けにDeepLink、セキュアな暗号化されたAIモデル共有にはTEN protocolと提携しています。
これらの統合により、音楽メタバース、ゲームなど多様なユースケースが、グローバルなGPUリソースによって支えられる道が開かれます。
なぜJanctionはAIの未来に適しているのか
AI需要が急増する世の中で、JanctionはGPUのような希少資源へのアクセスを分散化する点で際立っています。Akash Network(クラウドコンピューティング志向)やBittensor(AIトレーニング)とは異なり、JanctionはOptimism上のLayer2設定、EVM互換性、そしてJasmyのデータセキュリティに根ざした土台を持ち、完全なWeb3 AIエコシステムを目指しています。
資源スケジューリング、負荷分散、プライバシーといった大きな課題に取り組んでおり、日本のSociety 5.0のビジョンとも整合しています。テストネットは2025年2月から稼働しており、ブロックチェーンとAIが交差するあり方を形作るポテンシャルを秘めています。
ブロックチェーン実務者であれ、ミームトークンや技術のクロスオーバーに興味があるだけの人であれ、Janctionから目を離さないでください。こうしたBSCNewsのツイートは、AIの未来が分散化され、透明で、参加者全員に報いるものであることを思い起こさせます。詳細な技術仕様についてはオリジナルの投稿こちらを参照してください。