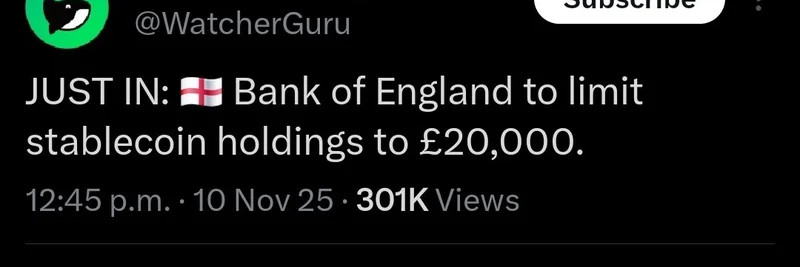皆さん、DeFi界隈に深くいるならご存知かもしれませんが、Hyperliquidが独自のネイティブステーブルコインUSDHを求めて動いている話題が盛り上がっています。これは単なるステーブルコインではなく、プラットフォームの将来を定義しうるティッカーであり、高速トレードと実用性を両立する可能性があります。DefiIgnasのツイートが端的に示す通り、企業系の大物と純粋なDeFiイノベーターの対決です。ここではコーヒー片手に話すような感じで、一つずつ整理してどちらに分があるか見ていきましょう。
まず簡単な説明を。Hyperliquidは独自のレイヤー1上に構築された分散型のパーペチュアル取引所で、超高速の取引と低手数料が特徴です。現在、公式のドル連動ステーブルコインUSDHを誰が発行するかを投票で決めようとしています。勝者はエコシステムに深く統合され、採用を一気に加速させる可能性があります。提案は続々と出ており、コミュニティのDiscordは議論で賑わっています。DefiIgnasがハイライトした主要候補に沿って、私なりの解説を加えます。
Native Markets:Hyperliquid第一主義の挑戦者
まずはNative Markets。彼らは初日からHyperliquidに全振りしているチームで、HyperEVM(Hyperliquidのスマートコントラクト層)経由でUSDHを発行し、コアチェーンにブリッジする計画です。注目点は、リザーブがBlackRockやSuperstateのような大手によってブリッジ構成で裏付けられていること、そして米国、EU、BVIでの規制上の承認を得ている点です。ステーブルコインの信頼という点では大きな強みになります(過去のUSDT騒動のような問題を思い出す人も多いはずです)。
利回り分配はコミュニティ寄り:50%がAssistance Fund(エコシステム成長のための助成金等に充てる)、残り50%がUSDH拡大に使われます。チームは豪華で、元Uniswap COO、元Paradigmの研究者、Hyperliquid支持者が揃っています。UnitがHyperliquidネイティブプロジェクトとして成功しているのと似たフィット感があります。ただしDiscordでは「Hyperliquidでの実績がないのでは?」という指摘も出ています。逆に勝てばHLホルダー向けの大きなエアドロップ期待もあるでしょう。Polymarketではオッズ45%、取引量は$12.9Kとしっかりしています。
Paxos:規制対応の大手
安全性とスケールを重視するなら、Paxosが注目株です。彼らはPayPal USDやかつてのBinanceのBUSDを支えてきた実績があり、ステーブルコイン運用のノウハウは抜群。NYDFSの規制下にあり、MiCAにも準拠しているため、規制リスクを嫌う機関投資家にとっては安心できる選択です。彼らの提案はリザーブ利回りの95%をHYPE買い戻し(Hyperliquidのネイティブトークン)に直送し、5%だけを自分たちに残すというものです。
企業色が強くチェーン非依存なので、大口の資金をHyperliquidに置きたいホエール層には魅力的かもしれません。一方で、反体制的な ethos を掲げるプラットフォームには「堅すぎる」と批判する声もあります。それでもPolymarketのオッズは38%、$13.5Kのボリューム。安全牌か、それとも売り渡し扱いか――議論は分かれます。
Frax:オンチェーンの透明性を重視するDeFi純度
DeFi純粋派に向けてはFraxが魅力的です。自身のステーブル frxUSD と米国債で1:1の裏付けを行い、全てがブロックチェーン上で検証可能—ブラックボックスはありません。彼らはトレジャリー利回りの100%をHyperliquidユーザーに還元すると約束しており、プラットフォームの理念にぴったり合致します。
FraxはDeFi界での経験値は高いものの、Hyperliquidの大きな野心にはニッチすぎるのではという批判もあります。もし勝利すれば$FRAXホルダーには大きな恩恵となるでしょう。Polymarketのオッズはわずか3%、$6.1Kのボリュームでアンダードッグの扱いですが、過小評価は禁物です。
Sky:高利回りで魅せるDeFi大手
Sky(MakerDAO的なイメージを想起させる)は、Hyperliquidのリスクフレームワーク上にUSDHを構築する提案をしています。裏付けは米国債と、80億ドル規模のバランスシートにあるCollateralized Loan Obligations。利回りは魅力的で、HL上に保有されるすべてのUSDHに対して4.85%のリターンを提示しており、現在のトレジャリー利回りを大きく上回ります。これはユーザーのロイヤリティを高める設計です。
DeFiネイティブとして文化的にもHyperliquidにマッチします。買い戻しシステムをHL側にシフトしてさらに深く統合することも可能です。スレッド内でSkyのRuneが参加しており、経済性の配分(Hyperliquidが大半を得る)や「Hyperliquid Star」を使ったチェーン専用トークンファーミングの計画などを明確にしています。GENIUS Act周りのコンプライアンス懸念は残るものの、彼らは「Generator Agent」モデルで将来的な対応を図ると主張しています。オッズは11%、取引量は$2.6K。理念の一致という点では私も好感を持っています。
Agora:インフラ寄りのアプローチ
最後にAgora。彼らはState Streetをカストディ、VanEckを運用パートナーに据えたホワイトラベル発行者で、MoonPayやLayerZeroのようなオンボーディング周りのインフラ連携を持っています。収益分配はネット収益の100%をHYPE買い戻しかAssistance Fundに回すという方針です。
問題はステーブルコイン規模での実績がないこと。これがオッズを低くしており、現状7%($4.3K)に留まっています。World Liberty Financial(WLFI)が絡むという噂もあり話題性はありますが、現実味はやや低めに見られています。
Polymarketのオッズとコミュニティの空気感
ツイートのスクリーンショットはPolymarketの予測市場ダッシュボードを示しており、Native Marketsが45%でリード、続いてPaxosが38%となっています。ただし流動性は薄めなので過度に信用するのは禁物で、DefiIgnasも「参考にならない可能性」を指摘しています。投票の状況はflowscan.xyz/usdhでライブ追跡できます(必要ならスペースを削ってください)。コミュニティの反応は二分しており、DeFi純度を求める声(Sky、Frax)とエアドロップを期待する声(Native)、そして企業的影響を懸念する声(Paxos)が混在しています。
これは単なるティッカーの問題ではなく、Hyperliquidが自らのアイデンティティをどこに置くかの賭けでもあります――企業的スケーラビリティか、DeFiの反体制的精神か。どちらが勝ってもプラットフォームにとって新たな時代の幕開けになる可能性が高く、HyperEVMがより多くのdAppを可能にする点も考えれば注目度は高いです。パーペチュアルをトレードしている人やHLの成長を狙う人は投票の行方を見逃さないでください。投票は間もなく締め切られます。
あなたはどう思いますか?Nativeの整合性派、それともSkyの高利回り派?コメントで教えてください。より深いDeFi解説を見たいならMeme Insiderにぜひ残ってください—ミームを実利に変えるブロックチェーンの最前線を追っています。
(このスレッドを火付け役にしてくれたDefiIgnasに感謝—詳細はこちらをフォローしてください。)