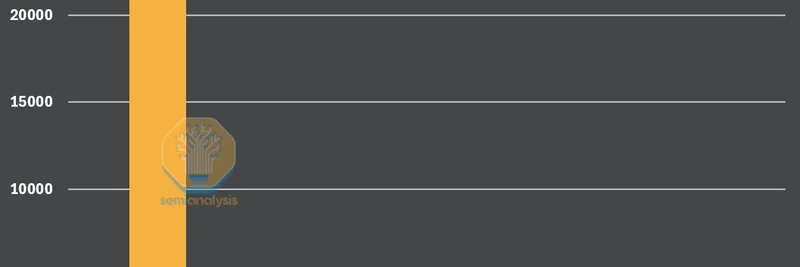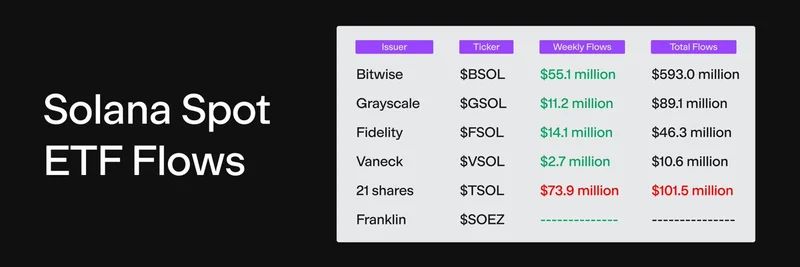急速に進化するテックの世界では、オープンソースはもはや単なる理想論ではなく、特に追い上げをかける側にとっては強力なビジネス戦略になっている。Dragonfly Capitalのマネージングパートナー、Haseeb Awanが最近のツイートで指摘したのはまさにその感触だ。彼は中国がロボティクスとAIの領域で既存の図式をひっくり返していると強調している。
Haseebはこう切り出している。「興味深い。かつて私はオープンソースをコンピューティングの哲学だと考えていたが、それは古い見方かもしれない。中国はチャレンジャーとして、単純にビジネス戦略としての価値に気づき始めている。」
彼はDeepSeekやQwenのような、中国発の強力なオープンソースAIモデルを例に挙げ、西側のクローズドなシステムに挑戦していると述べる。しかし、彼のスレッドで真の注目点となっているのはUnitree Roboticsへの言及だ。Unitreeは四足歩行ロボットの定番となっており、犬のように歩き、跳び、ナビゲートできる機械において存在感を放っている。
Haseebによれば、Unitreeは四足ロボットの世界市場シェアの約70%を握っているという。なぜか?それは彼らのロボットが手頃な価格であること、そしてオープンなSDK(ソフトウェア開発キット)を提供していることだ。このオープンさにより、研究者や開発者は面倒な手続きなしに簡単にカスタマイズや実験ができる。
これを、Spotのバックフリップで話題になった米国の雄、Boston Dynamicsと比べてみるとわかりやすい。彼らのロボットで深いレベルの制御を得るには年単位のライセンス費用を払う必要があることも多く、クローズドな設計は特に資金に余裕のない学術ラボでの普及を遅らせる可能性がある。
挑戦者にとってなぜオープンソースが勝つのか
Haseebの見立ては、Packy McCormickのニュースレターNot Boringで描かれている「Electric Stack」— バッテリー、モーター、電子機器といった、EVやドローン、ロボットに動力を供給する要素 — における中国の優位性という大きな構図と結びつく。中国は単に模倣しているのではなく、オープンなアプローチでエコシステムをスケールさせ、自国の製品にフィードバックを与える形で賢く拡大している。
ロボティクス分野では、Unitreeの戦略が研究コミュニティで光っている。例えばGo2モデルは、ANYmalやSpotといった競合より安価でありながら、実験で発生する衝突にも耐えうる堅牢性があるため好まれている。ラボは高額な修理費を恐れずリスクのある制御ポリシーを試せる。トップ大学がUnitree用のカスタムソフトを構築すれば、それが更なる採用を生み、コスト低下の好循環を促す。
これは、DeepSeek(コーディングに特化したLLM)やQwen(Alibabaの多言語に強いモデル)のようなAIモデルで起きていることと似ている。オープンソース化することで中国は世界中の開発者に改良や統合を促しつつ、ハードウェア面での優位は社内に留めている。
ブロックチェーンとミームトークンへの類似点
CoinDeskで暗号資産を追いかけ、現在はMeme Insiderでミームトークンを扱う者として見ると、ブロックチェーン領域にも同様の反響がある。オープンソースは暗号の基盤だ — Ethereumのコードは自由にフォークでき、その結果Solanaや数え切れないミームコインのようなイノベーションを生んだ。
ミームトークンもこのオープン性で成長する。Dogecoinのようなプロジェクトはジョークとして始まったが、誰でも上に構築したりコミュニティを作ったり、派生をフォークしたりできることで爆発的に広がった。UnitreeのSDKと似た構造で、参入障壁が低いほど実験が加速し、基礎を押さえれば市場支配につながる速さが出る。
しかし裏側もある—オープンソースはコピーや競争を生む。西側の技術が中国で「吸収」される(リバースエンジニアリングされ改善されるという婉曲表現)ように、ミームトークンの開発者は成功したコントラクトをフォークして、時にはラグ(rug)や希薄化を引き起こすこともある。それでも勝者は、強いコミュニティを築き素早く反復できる者だ。Unitreeが研究からのフィードバックでコストを叩きつつ市場を圧倒しているのと同じだ。
ロボティクスと暗号資産の今後は?
今後、中国主導のオープンソース推進はロボティクスとブロックチェーンの交差点で思いもよらぬ形で結びつく可能性がある。分散化されたAIがUnitreeの群れを制御し、ミームコインでトークン化される世界を想像してみてほしい。あるいはカスタムロボットSDKへのアクセスをNFTで gated にする、といったことも考えられる。まだ初期段階だが、中国のようなチャレンジャーが示す通り、オープンさは慈善ではなく戦略だ。
Haseebのスレッドはオープンソースを「ソフトパワー」と捉える反応を呼び、Electric Slideの記事などの深掘りにリンクする声も上がった。あるユーザーはUnitreeがサプライチェーンを握ることで価格を低く抑えられている点を指摘し、これはEVや太陽光といった中国の広域戦略と響き合っている。
ブロックチェーン関係者はこうしたハードウェアトレンドを注視しておくべきだ。次のミームトークンの物語はここから生まれるかもしれない――ロボット犬があなたのポートフォリオをポンプする日が来るかも。暗号の世界では奇妙なことほど現実になる。
テック戦略がミーム生態系にどう影響するか、より詳しく知りたいならMeme Insiderに残ってほしい。Unitreeのロボットのようなスピードで動くトークンに関するアルファを握っている。