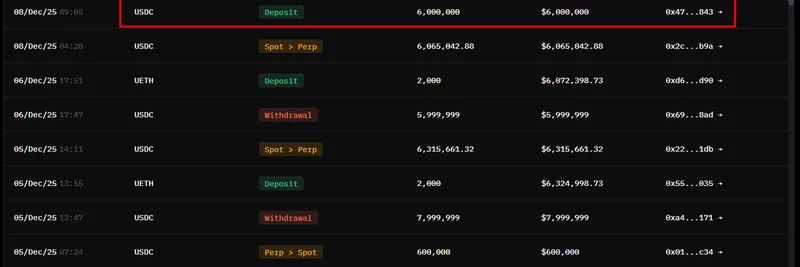急速に動く暗号資産の世界、特にミームトークン領域では、収益の扱いが伝統的な金融とは大きく異なる道を辿ることが多い。Solanaエコシステムで著名な人物であり、Frictionless CapitalとMonkeDAOの共同設立者兼マネージングパートナーであるSolana Legendの最近のツイートは、この明確な対比をユーモラスかつ洞察に富んだ形で浮き彫りにしている。
彼はこう指摘している:「伝統的な金融では、投資家より高いリターンを生むために再投資できないと思う場合にだけ配当を出すし、株が非常に過小評価されていると思えば買い戻しを行う。暗号では、人々は収益を上げたらすぐに買い戻しやバーンをやる lol。」
この観察は、MonkeDAOのようなSolana上のプロジェクトや、BONKやWIFのような人気ミームトークンを追っている人々に深く響く。これらのプロジェクトは、収益を得るやいなやほぼ即座に買い戻しやトークンのバーンを発表することが頻繁にある。しかし、なぜ急ぐのか?そしてミームトークンの支持者は、より賢明な投資判断を下すために伝統的金融の原則から何を学べるのか?
暗号におけるBuybacksとBurnsの理解
まず、業界に不慣れな人のために用語を分解しよう。暗号におけるbuybackは、プロジェクトが収益を使って市場から自分たちのトークンを買い戻し、供給を減らして価格を押し上げる可能性を作る行為を指す。一方、burnはトークンをデッドウォレットに送るなどして恒久的に流通から取り除くことを意味する。どちらの仕組みもミームコインで人気があるのは、デフレ圧力を生み、コミュニティを盛り上げて短期的な価値を高める効果があるからだ。
たとえば、MonkeDAOエコシステム内の人気SolanaベースのミームトークンやBONK、WIFのようなプロジェクトは、取引手数料、NFT販売、パートナーシップなどで収益を生むことが多い。開発や拡大への再投資を行う代わりに、多くはバーンを選び、ホルダーに即座に報いる。これは、皆にパイの一切れをすぐに配るようなもので、雰囲気を盛り上げ、FOMO(乗り遅れる恐怖)を高め続ける効果がある。
伝統的金融の視点
対照的に、伝統的金融は配当や自社株買いをより慎重に扱う。配当は利益から株主に支払われるが、AppleやAmazonのような企業は、現金を研究開発、買収、事業拡大などの内部的な用途に回せる自信がある限りは配当を出さないことが多い。自社株買いは、経営陣が株式が過小評価されていると判断したときに行われ、将来の成長に賭ける行為だ。
この規律は長期的な株主価値の最大化という受託者責任に根ざしている。利益を再投資することで時間をかけてリターンを複利化できれば、良い会社を偉大な会社へと変えることができる。ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイはその典型例であり、配当を避け、最も高いリターンを生むと考えられるところに資本を配分することを好む。
なぜ暗号プロジェクトは買い戻しやバーンに飛びつくのか
では、なぜ暗号、特にミームトークンの世界は脚本をひっくり返すのか。いくつかの理由が際立つ:
コミュニティ主導の盛り上がり:ミームトークンはソーシャルモメンタムで生きている。バーンや買い戻しを発表するとX (formerly Twitter)などで話題になり、新規購入者を引き寄せて価格を押し上げる。注意力の移ろいやすい市場での短期的な勝利だ。
規制の欠如:上場企業と同じ監督がないため、暗号プロジェクトはより自由に動ける。衝動的な決断を招くこともあるが、初期採用者に報いる革新的なトークノミクスを実験する余地も生まれる。
トークノミクス設計:多くのミームコインは初めからデフレメカニズムを組み込んでいる。Shiba Inuのようなプロジェクトはバーンを広め、手数料の一部が自動的に供給を減らすことで自己持続的な盛り上がりを作ることを流行らせた。
短期志向:ボラティリティの高い市場では、創業者は流動性やコミュニティの忠誠を維持するために即時的な価値付与を優先し、長期的な持続可能性を後回しにすることがある。
しかし、このアプローチにはリスクもある。バーンに過度に依存すると、革新的な成長戦略の欠如を示すシグナルとなり、最初の興奮が冷めた後に停滞を招く可能性がある。
ミームトークン投資家への示唆
ブロックチェーン