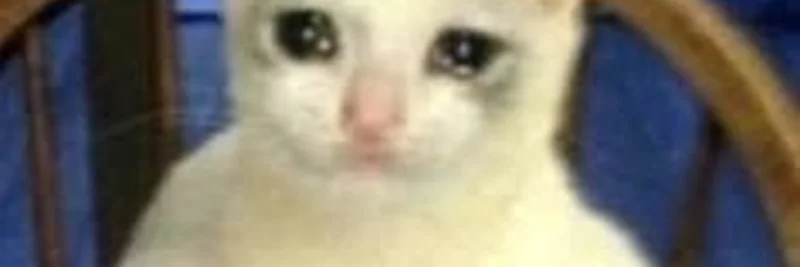高速で動くCrypto Twitter(略してCT)の世界で、テック系クリエイターの@ashen_sol1による最近の投稿が、インフルエンサーの誠実性の低下についての議論を呼び起こしました。そのツイートは、ほぼすべての著名人がミームコインをローンチまたは宣伝し、結果的に「rug(ラグ)」した――つまりプロジェクトを放棄して資金を持ち去ることで投資家の足元をすくう――という問題のある傾向を指摘しています。
@ashen_sol1はこちらでこう共有しました:「正直、CTの大物のほとんどがコインをローンチしたり煽ったりして、いつかはラグしてるって状況になってるんだ。未だにやってない人はごく少数、たぶん10%くらいしかいない。ここ2年で道徳規範はかなり大きく変わったと思う。」
用語に不慣れな人のために説明すると、「rug pull(ラグプル)」はDeFiやミームトークンのエコシステムでよく見られる詐欺です。プロジェクトの作成者がトークンを盛り上げて投資を集め、突如として流動性をすべて引き上げることでトークンの価値をほぼゼロに落とし、得た資金を持ち去る手口です。SolanaやEthereumのようなブロックチェーン上で作られることが多いミームコインは、バイラル性が高く基礎的なユーティリティが乏しいため、特に狙われやすい傾向にあります。
この指摘は、DogecoinやSolana上の新しいプロジェクトなどミームトークンが注目を集めているタイミングで出されました。ただし、Pump.funのようなプラットフォームで簡単にトークンを立ち上げられることがハードルを下げ、短期間での詐欺を可能にしています。@ashen_sol1の「大物のうち未だにそうしたことをしていない人は約10%しかいない」という推定は、文化の変化を強調しています。2年前はコミュニティは分散化や信頼不要なシステムを重視していましたが、今は短期的な利益が優先されているようです。
ツイートへの返信も同じような感想であふれていました。@HavelsJordansは冗談めかして下品な名前のコインを出すことを勧め、倫理に対する気軽な姿勢を浮き彫りにしました。@Mackypeeeは「良心ゼロだ」と嘆き、@khing_ladipoeは単純に「その通りだよ」と同意しました。@lusevi4は「誠実さは二の次になった」と指摘し、@anakincocoは「誰だって何でもやるよ(笑)、払われる金額次第だ」と述べました。
一方で、@_SirJoeyの返信は個人の誠実さを強調していました:「私は大物じゃないけど、とにかくコインを落としたりラグしたりしたことはないし、たとえ大物でもそんなことはしない。誠実さは守らないと。」これは支配的な傾向とは対照的で、まだ高い基準を保っている少数派がいることを示しています。
@mangusxbtは「ashencoin67の時間だ」とからかい、将来のローンチの可能性を仄めかしました。@xiaopao718は「the great shillingだ。誠実さが新たなエッジだ」と振り返りました。
この議論は、ミームトークンを扱うブロックチェーン実務者にとって非常に重要です。Meme Insiderとしては、デューデリジェンスを推奨します:プロジェクトの流動性ロック、チームの透明性、コミュニティのセンチメントを投資前に確認してください。DexscreenerやRugcheckのようなツールは、レッドフラッグを見つけるのに役立ちます。ミームコインは楽しさや利益の可能性を提供しますが、CT上での道徳観の変化は一つの警告でもあります―この暗号のワイルドウェストでは「信用はするが確認する(trust but verify)」ことを忘れないでください。