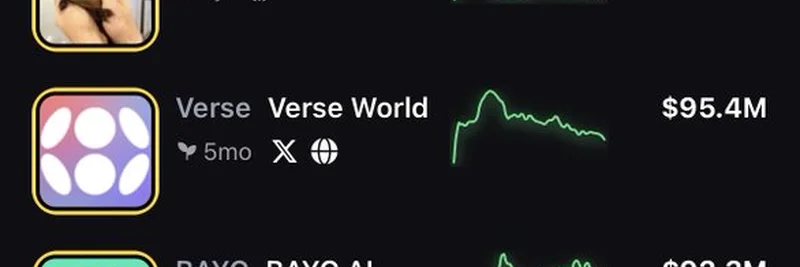急速に進化するWeb3の世界では、ブロックチェーンに関心を持つ人々がインターネットさえあればどこからでも取引し、調査し、構築できる一方で、リモートワークの有効性を巡る議論が白熱しています。最近のX(旧Twitter)でのやり取りは、この緊張を浮き彫りにし、監督を重視する従来の見方と自己駆動的なクリプトコミュニティの倫理観を対立させました。
議論は@redhairshanks86の投稿から始まりました。投稿者は、多くの人にとってリモートワークは単にうまくいかないと主張しました。オフィスでの監督がなければ大半は手を抜く――複数の仕事を掛け持ちしたりサイドプロジェクトに取り組んだりする開発者がいる一方で、他の人は勤務時間中にオンラインショッピングをしたりジムに行ったりする、というのです。これを、中央のリーダーシップを持たないブロックチェーンベースの集団であるDAOs(分散型自律組織)が失敗しがちな理由に例え、監督がないと怠惰がはびこると強調しました。
しかし、全員がそう考えているわけではありません。ここで登場したのが@sol_nxxn。自称「Solanaのグリーンナイト」でありArciumの貢献者でもある彼は、Web3での地道な努力に根ざした見解で反論しました。彼の指摘では、暗号世界の多くはリモートで機能しており、取引や調査、制作を自宅から行っているといいます。肝心なのは「ハングリー(hungry)」なマインドセット――十分な収入を得る前に成功を目指すそのドライブです。Solana上のmeme tokensのようなボラティリティの高い市場で得られる可能性を見越して、この野心が人々をWeb3に引き寄せている、というわけです。
このマインドセットは、少額の投資を人生を変えるほどの利益に変え得るスピード感と常時の注意力が求められるmeme tokenの世界で強く共鳴します。高速で低手数料が特徴のSolanaのようなプラットフォームは、リモートのクリエイターがオフィスに一度も足を踏み入れることなくトークンを立ち上げ、プロモートすることを可能にします。考えてみてください:バイラルなトレンドに触発されたmeme coinsはコミュニティの盛り上がりで繁栄し、しばしばタイムゾーンに散らばった分散チームによって作られます。
スレッドへの返信も似たような意見を反映していました。あるユーザーは、見返りの約束が意欲的な人材をWeb3に引き寄せると指摘し、別のユーザーは問題なのはリモート環境そのものではなく「comfort plateau(快適な停滞)」に達することが生産性の本当の殺し屋だと述べました。
この議論の核心は、ブロックチェーンにおける働き方への見方が変わりつつあることを示しています。伝統的な職場では上司の目が生産性を支えることがあるかもしれませんが、クリプトの世界では金銭的自由の魅力に駆り立てられた内発的動機が主導することが多いのです。次の大きなmeme tokenを狙うブロックチェーン実務者にとって、「ハングリー」でいることが、忘れ去られるか成功の波に乗るかの差になるかもしれません。
もしSolanaに飛び込んだりmeme tokensを探っているなら、覚えておいてください:生産性は「どこで働くか」ではなく「なぜ働くか」です。そのマインドセットを研ぎ澄ませれば、Web3におけるリモート革命はあなたのために機能するかもしれません。