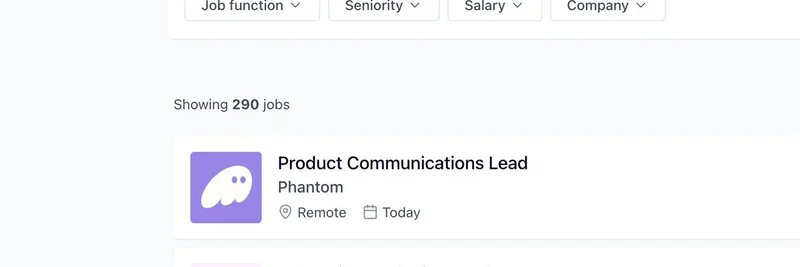暗号の世界では物語が瞬く間に広まりがちで、最近話題になっているのが、Hyperliquid(独自のLayer-1チェーン上で動く最先端の分散型永久先物取引所)のネイティブトークンである$HYPEが「過度に保有(overowned)されている」という考えだ。しかし、DeFi界隈で信頼されている声の一つである@defi_monkの最近の投稿によれば、これは事実からかなり離れている。彼の重要な指摘を分解して、なぜ$HYPEにまだ成長余地があるのかを見てみよう。
Defi_monkはまず過度保有という主張に正面から異議を唱え、オンチェーンの分布データでそれを裏付けている。オンチェーンデータとは、トークンがどのウォレットにどう保有・移動されているかを示すブロックチェーン上の透明な記録だ。X(旧Twitter)上の一部の声の大きいコミュニティでは「みんな$HYPEを持っている」ように見えるかもしれないが、現実は異なると彼は主張する。経験則としても、Hyperliquidのコアエコシステム外(しばしば「.hls」やHyperliquidネイティブと呼ばれる)にいる人々にアンケートを取ると、彼らの割当はせいぜい控えめだという。
彼が強調する大きな要因の一つは、パッシブな保有者の存在だ。これらは市場サイクルを通じて$BTC、$ETH、$SOLといったブルーチップ資産で巨額の未実現利益(uPNL)を積み上げてきた投資家たちだ。8桁や9桁の利益を抱えている人々がまだ完全に$HYPEへローテーションしていない可能性がある。さらに重要なのは、$HYPEはまだ流通開始から1年未満であり、税務上の影響が絡む点だ。確立された保有資産を売却して比較的新しいトークンである$HYPEを買うと大きなキャピタルゲイン税が発生する可能性があり、大口のプレイヤーは慎重になりがちだ。
加えて、初期に大量の供給を掴んだ多くのOG(オリジナル勢)は、既に保有を高い価格で新規参入者に分配している。これにより所有権はより高い取得価格で買った保有者に移り、彼らは初動の下落で投げ売りしにくくなる。Defi_monkは、これらの売り手は平均的なミームコインのフリッパー(短期売買する人)ではなく、価格が魅力的に下がれば買い戻すような戦略的プレイヤーだと指摘している。@ThinkingUSDをこの「安く買って高く売り、下がれば買い戻す」メンタリティの代表例として挙げている。
また、X上のエコーチェンバー効果にも彼は反論する。Hyperliquidの支持者がオンラインで声高に叫んでいるからといって、より広い暗号通貨世界が過度に暴露されているわけではない。実際、このコミュニティは「相対的に小さく貧弱(relatively small and poor)」であり、空間の巨大プレイヤー—何十億ドルもの$SOLを持つファンドやテック系億万長者、何十億ドル規模の$ETHを持つTom Leeのようなクジラ、そして終わりのない$BTCマキシマリストの流れ—と比べれば取るに足らない。こうした外部の巨大な購入者(exogenous bidders)は現在の$HYPE保有者基盤をはるかに凌駕する可能性がある。
流動性のあるファンドやベンチャーファンドの間でも、$HYPEへの割当は概して慎重だ。多くはHIP-3の含意(おそらくガバナンス、staking、エコシステム機能のアップグレードなど、トークンのユーティリティを高めうる改善提案)をようやく認識し始めている段階にある。これらのファンドは個人トレーダーよりもコストベースが高いことが多く、短期的なフリップではなく中長期で保持するつもりでいる。
最後に、@Citrini7や大手メディアのCNBCのような主流メディアが$HYPEを取り上げ始めると、巨大な新規買い手層への扉が開かれる。こうした露出は伝統的な金融や小口のリテール投資家といった現在のサークルを超えた新たな資本を呼び込む可能性がある。
では、ミームトークン愛好家やDeFi実務者にとってこれは何を意味するのか?$HYPEは強いコミュニティと急速な採用でミーム的な拡散力を持っているが、永久先物取引という実利のあるテクノロジーに支えられている。defi_monkの見立てが正しければ、配布段階はまだ初期であり、流入を待つ未開拓の流動性プールが残っている。ブロックチェーントレンドに関するナレッジベースを構築している人にとって、$HYPEのオンチェーン指標やコミュニティのセンチメントを監視することは次の大きな機会を見つける手助けになるだろう。
全文は元の投稿をチェックしてスレッドに参加してみてほしい。いつものように、これは金融アドバイスではない。必ずご自身で調査(DYOR)を行い、この常に変化する領域で情報を更新し続けてほしい。