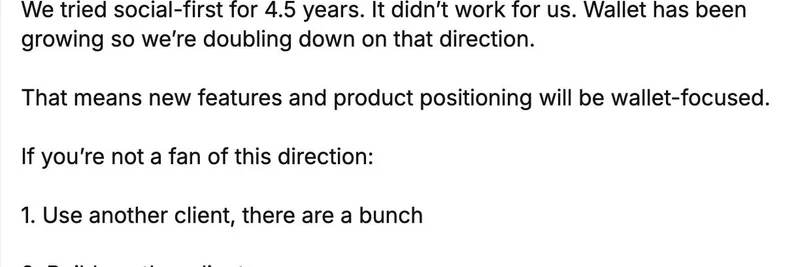こんにちは、クリプト愛好家の皆さん!ブロックチェーン界の最新動向を追っているなら、BSCNewsが最近ツイートしたInterLinkのトークノミクス分解を目にしたかもしれません。ポイントは$ITLと$ITLGによる二重トークン体制で、これがユーザードリブンなネットワークの考え方を変える可能性があります。特にコミュニティが重要なミームトークン界隈では注目に値します。ブロックチェーン博士でなくても分かるように、分かりやすく解説します。
InterLinkのトークノミクスが際立つ理由は?
InterLinkはありふれたプロジェクトではなく、「人間中心(human-centric)」のネットワークを軸に構築されています。つまり、大口ウォレットやボットではなく、実在の人間—検証済みユーザー—に焦点を当てているということです。2025年6月中旬にアップデートされたホワイトペーパーで、この二重トークンモデルが導入されました。なぜ2つのトークンなのか?それは、投資の側面と日常的なユーティリティを分離することで、システム全体をよりバランスよくし、SECなどの規制にも対処しやすくするためです。
イメージとしては、$ITLがビットコインに似た「store of value」的な存在で、$ITLGがEthereumのガスのような「実務遂行」トークンだと考えてください。この仕組みは10億(1 billion)の検証済みユーザーのオンボードを目指し、proof of personhoodに基づいて配布されます—一人につき一ノード、一回限りの報酬チャンス。高価なマイニング機材で早期に恩恵を受ける人だけが報われる時代は終わり、真の人間の参加が重視されます。
$ITLの内訳:戦略的リザーブトークン
まず$ITLです。このトークンの総供給量は10 billionで、希少性と価値を保つ設計になっています。その半分(5 billion)は$ITLG保有者向けに留保され、残りの半分は機関向けの成長とエコシステムの安定化に充てられます。InterLink Foundationによって管理される$ITLはstakingに最適化されています。ステーキングを通じて、パートナー、プラットフォーム、さらにはベンチャーキャピタルのような大口プレイヤーも「Human Layer」—検証済みユーザーのネットワーク—にアクセスできます。
簡単に言えば、機関やプロトコルビルダーにとって$ITLは信頼できる実在人間のプールにアクセスするための切符です。短期的な売買よりも、信頼性と安定性を重視した長期保有を想定しています。
$ITLG:日常ユーザー向けのユーティリティ中核
次に$ITLGです。こちらは総供給量が100 billionと遥かに多く、80%が「Human Node miners」—つまり検証を経たユーザーが、認証や友人紹介などのアクションで獲得するために割り当てられています。残りの20%はネットワークを活性化するためのインセンティブに使われます。
$ITLGで何ができるのか?ガバナンスではDAO投票を通じてプロジェクトの意思決定に参加できます。新規プロジェクトのローンチパッドへの早期アクセス権が得られたり、ネットワーク内のミニアプリ(ゲームや各種サービス)での支払いにも使えます。さらに$ITLGを保有することで$ITLを併せて獲得できる仕組みもあり、魅力が増します。全供給がマイニングされた後は、保有者が供給上限を維持するか成長のために拡張するかを投票で決めます。
マイニングの仕組み:参加しやすく、ボット対策済み
InterLinkでのマイニングはとてもシンプルで、初期段階から誰でも参加しやすいように設計されています。Human Nodeになるには本人確認(顔認証など)でボットでないことを証明します。報酬は認証や紹介といったアクティビティから得られ、早期参加者と新規参加者のバランスを取る動的な仕組みになっています。
公平性を保つために、トークンロック機構とベスティングスケジュールが組み込まれており、マイニングで得たトークンが一度に市場に放出されないようになっています。検証と報酬の調整を通じてインフレを抑制し、持続可能性を意識した設計です。
実世界へのインパクト:単なる暗号通貨を超えて
これは単なる理論ではありません。InterLinkのモデルは、従来の金融サービスで取り残されがちな人々に対して実用的な応用例を持っています。世界には世界銀行のデータによれば14億人以上のアンバンクド成人が存在し、$ITLGはスマートフォンだけでピアツーピア決済を可能にする手段を提供し得ます。災害地域でNGOが検証済みの人々に直接支援を送ることで、詐欺や中間業者を排除できる想像は簡単です。
また、WHOやUNICEFのような組織を通じた健康・教育向けのマイクログラントにも使えます。Googleのような大手テック企業がAI学習用データの提供に対してユーザーに$ITLGで報酬を支払う、といった倫理的なデータ取引の事例も考えられます。バイラル性とユーティリティが交差するミームトークン界隈では、この「人間中心」の焦点が、過熱した話題よりも実際のコミュニティを重視するプロジェクトを促すかもしれません。
まとめ:InterLinkはユーザードリブンな暗号の未来か?
InterLinkの二重トークンモデルは、セキュリティとユーティリティを賢く組み合わせ、真に分散化された人間主導の経済を作ろうとしています。笑いを目的としたミームトークンでも、技術志向の真剣なブロックチェーンでも、学ぶ点は多いでしょう。成功の鍵は採用率、規制対応、そしてマイニングやガバナンスがどれだけうまく機能するかにかかっていますが、10億ユーザーというビジョンは野心的でワクワクします。
興味が湧いたら、元のBSCNews記事で詳細をチェックするか、最新情報は@inter_linkをフォローしてください。皆さんはどう思いますか—このモデルはミーム界隈でも広がるでしょうか?下に感想をぜひ書いてください!