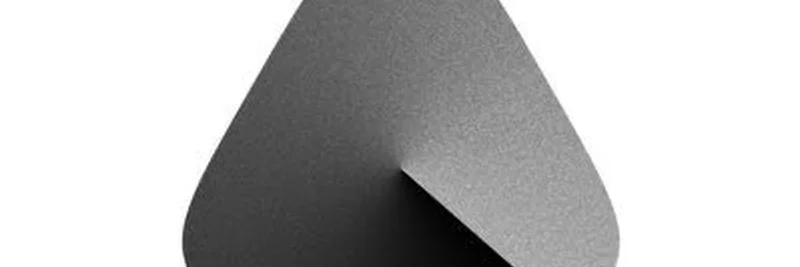暗号通貨の世界は一夜にしてトレンドが爆発し、あっという間に消えてしまうことがあるため、従来のプロダクト開発の考え方はしばしば物足りなく感じられます。@darkresearchai、@mtndao、@paladin_solana での活動で知られる暗号領域の有力者 Edgar Pavlovsky が X に投稿した最近の投稿は、重要なマインドセットの転換を示しています。Railway の Jake が「ローンチは一度きりのイベントではなく、むしろ40回に近い反復だ」と強調した言葉を引用し、Pavlovsky はこの考えをミームトークンの制作者やブロックチェーン愛好家に深く響く形で拡張しています。
Pavlovsky は「最終的なローンチ」など存在しないと主張します。代わりにそれは継続的なプロセスであり、最初のローンチ、2回目、3回目と無限に続いていくのです。このアプローチは、インターネットユーザーから迅速なフィードバックが得られ、反復の障壁がかつてないほど低い今日の「配布ファースト」環境に非常に適しています。Solana や Ethereum のようなプラットフォーム上で、しばしばユーモアやバイラルなアイデアとして始まるミームトークンにとって、この哲学は単なる助言ではなく生存戦略です。
考えてみてください。Dogecoin や Shiba Inu のようなミームトークンは、一度の完成されたリリースで大成功を収めたわけではありません。コミュニティのインプット、アップデート、リローンチを通じて進化し、話題性を維持してきました。例えば Dogecoin は2013年にジョークとして始まりましたが、その後の繰り返しの支持や統合、さらには市場の要求に応じたフォークを通じて勢いを増しました。同様に、pump.fun などから生まれる Solana 上の新しいミームは、最小限の実行可能プロダクト(MVPs)で素早くローンチし、Telegram グループや X スレッドを通じてフィードバックを収集し、ほぼ毎日のように反復して tokenomics を洗練したりユーティリティを追加したり、ナラティブをピボットさせたりします。
この反復モデルは、ブロックチェーンの分散的な特性と完全に合致します。従来のソフトウェアではアップデートに数ヶ月かかることがある一方で、smart contracts やトークン標準は迅速な変更を可能にします—場合によっては governance votes や単純な redeployments によってです。Pavlovsky が指摘するように反復コストが低いという点は的を射ており、Solana の高スループットなネットワークのようなツールは、開発者が多大なコストをかけずにテストや調整を行うことを可能にします。
ミームトークンを作ろうとする人への教訓は明白です:完璧を待つな。早くローンチし、コミュニティの声に耳を傾け、継続的に出し続けろ。これによって勢いが生まれるだけでなく、プロジェクトの進化に関与していると感じるホルダーの忠誠心も育まれます。Pavlovsky の言葉を借りれば、素晴らしいものにするためにローンチし、それを保つためにローンチし続けるのです。
ミームトークンのエコシステムでは、バイラリティが王です。終わりなきローンチを受け入れれば、単純なアイデアが文化的現象に変わる可能性があります。もしあなたが暗号分野で何かを作っているなら、この知恵に耳を傾けてください—次の反復がバイラルになるかもしれません。
オリジナルのスレッドはこちらで確認できます。