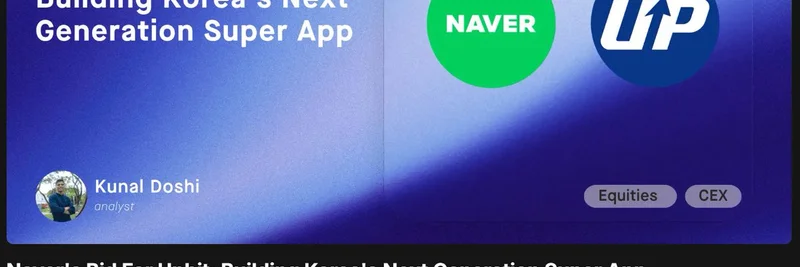Ethereum Name Service (ENS) がブロックチェーン界で再び話題になっています。最近Xでの発表において、ENSチームはNamechainをNethermindのSurgeへ移行すると明かしました。SurgeはTaiko stackで動作する最先端のbased rollupフレームワークです。この一手は、分散化(decentralization)、高速なファイナリティ(quick finality)、検閲耐性といったENSの中核的な原則へのコミットメントを強く示すものであり、同時にEthereum上でネイティブに決済(settle)される点も重要です。
用語に馴染みがない人のために説明すると、NamechainはENSがドメイン名の登録や管理をより効率的に扱うために設計したLayer 2(L2)ソリューションです。Rollupsは簡単に言えば、トランザクションをメインのEthereumチェーンから束ねてオフチェーンで処理し、コストを下げて速度を上げ、最終的にセキュリティのためにEthereum上で決済するスケーリング技術です。based rollupsとは、シーケンシングにEthereum自身のバリデーターを活用し、最初から真の分散化を促進するタイプを指します。
ENSの投稿は、多くのLayer 2ネットワークが抱える問題点を指摘しています:彼らはしばしば「漸進的な分散化(progressive decentralization)」を約束しますが、完全な分散シーケンシングのような難しい部分を将来へ先送りにしてしまいがちです。Surgeはその構図を変えます。これによりNamechainは「stage 1」のロールアップとしてローンチでき、すでにある程度分散化された状態で開始し、「stage 2」へと進むロードマップも明確です。stage 2では中央オペレーターが決定権を持つことなく、完全な分散化が機能します。
ここで注目すべき革新の一つが、CCIP-Readのパフォーマンス向上です。CCIP-Readは安全なクロスチェーンのデータ読み取りを可能にするプロトコルで、ドメイン名の更新をほぼ即時に反映してほしいと期待するENSユーザーにとって非常に重要です。従来のrollupでは状態更新に何時間もかかることがありましたが、based rollupsとpreconfirmations(早期トランザクション保障)、trusted execution environments(信頼できる実行環境)を組み合わせることで、NethermindとENSはその時間を数秒に短縮しました。これにより、ミームトークンのように素早く覚えやすい名前が重視される分野も含め、ENSドメインはより日常的に使えるものになります。
技術的な詳細に興味がある方は、ENSチームの最新ブログ記事を参照してください: 詳しくはこちら。この移行はEthereumの理念と一致するだけでなく、堅牢でスケーラブルな分散化を目指す他プロジェクトにとっての前例にもなり得ます。
常に変化する暗号通貨の世界において、今回のような動きはなぜENSがweb3のアイデンティティ基盤として重要であり続けるのかを改めて示しています。遊び心のあるミームドメインを登録するにせよ、真剣なdAppを構築するにせよ、高速で安全なネーミングは誰にとってもメリットです。ブロックチェーン技術とミームやトークンの交差点に関する最新情報は、今後もMeme Insiderでお届けします。