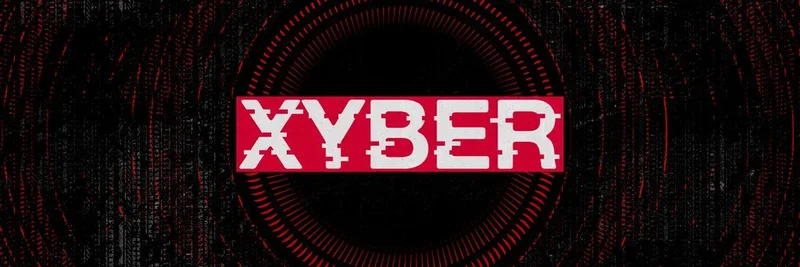Hey there, meme enthusiasts and blockchain builders! もしEthereum上でのミームトークンローンチが高いガス代に足を引っ張られてイライラしたことがあるなら、あなたは一人ではありません。Ethereumのメインネット(Layer 1、略してL1)のスケーリングは長く議論されてきた話題で、Ethereum Foundationの研究者Toni Coratgerの最新スレッドが、今後のロードマップを非常に明確にしてくれました。Frontiers 2025でのAnsgar Dietrichsの講演を踏まえたこの解説は、ハードウェア要件を跳ね上げずにEthereumをより高速で効率的にすることに焦点を当てています。段階を追って解説し、ミームトークンの世界にとってなぜ重要なのかを見ていきましょう。
The Big Picture: Scaling as a Multi-Layered Stack
EthereumのL1スケーリングは単発の魔法の解決策ではなく、異なるタイムラインで進む並行した取り組みの集合です。ゲーム用PCのアップグレードを想像してください:一部はソフトのクイック修正、他は新しいハードウェアが必要、そして大きなものはシステム全体を作り変えます。
- Short-term wins: ネットワーク全体のアップグレード(ハードフォーク)を必要としないクライアント性能の改善。既存の環境からより多くを絞り出すことが目的です。
- Medium-term plays: フルノードでのブロック検証を高速化するための年次ハードフォークによるプロトコル調整。目標は、誰にでも高性能なマシンを買わせることなくTPSを向上させること。
- Long-term visions: リアルタイムZKVMのようなゲームチェンジャー。実現までに数年かかる可能性がありますが、非常に大きな効率化を約束します。
これらはそれぞれ異なる速度で並行して進みます。ミームトークン開発者にとっては、トランザクション速度とコストが着実に改善されるということで、プロジェクトをバズらせやすくなります。
Zooming In on Medium-Term Magic: Optimizing Block Verification
スレッドはミディアムタームに深く入り込み、フルノード(すべてのトランザクションを検証するコンピュータ)により多くを処理させるための最適化に注力しています。最適化すべき主要リソースは、ブロックをダウンロードするための帯域、トランザクション実行とstate root計算(ブロックチェーン台帳のスナップショット)に必要な計算、そしてデータの読み書きに使うディスクI/Oです。
現在の仕組み:Ethereumは約12秒ごとにブロックを生成しますが、検証は多くの場合約4秒で終わり、余った時間が生まれます。計画はこの検証ウィンドウを伸ばすことで、enshrined Proposer-Builder Separation(ePBS)や遅延実行のような手法を使い、スロット時間をより効率的に使えるようにすることです。
さらに、ダウンロード→実行→root算出という厳密な逐次処理をやめて、並行させます。ブロックが触るであろうstateデータを"access lists"で事前に発表しておけば、ノードは実行中に事前取得(prefetch)できます。パーティーの前にプレイリストを先に読み込んでおくようなものです。
Unlocking Parallelism with Multi-Dimensional Metering
ここからが巧みな部分です。重複を許しても、その余剰能力を実際に利用できるようにする必要があります。そこで登場するのが多次元ガスメータリング:今日の単一ガスカウンターは維持しつつ、リソース種別(compute、state、data)ごとに「色付け」し、それぞれ別に上限を設けます。これによりアイドル状態の容量を安全に実効スループットに変換できます。
クライアントチームは既に遅いオペレーションを見つけて最適化し、ブロックあたりのガス限界を45Mから60Mなどへ引き上げるループにあります。しかしプロトコル側の対処としては、再価格付け(repricing)を検討中:安価な操作はさらに安く、特定のprecompilesのような高コストな操作は高くすることでスパイクを平滑化します。
鍵は、リソース間の相対価格を正しく設定し、あるリソースが過剰消費されて他が使われない状況を避けることです。ミームトークンにとっては、これが盛り上がり時の手数料をより予測可能にし、小口のトレーダーが高騰で被弾するリスクを減らしてくれます。
Fee Market Tweaks and Parallel Execution
EthereumのEIP-1559手数料メカニズムはブロック充填率50%を目標にして安定した需要信号を出しますが、これでは潜在的なTPSが使われていない状態です。検討案としては、即時効果を狙って目標を60〜70%へ引き上げるか、長期的には手数料ターゲティングの全面的な見直しがあります。
実行面では、楽観的アプローチ(コンフリクトがないと仮定して、問題があればフォールバックする)よりも決定的な並列実行が優勢です。access listsとstate diffs(変更分)を活用すれば、トランザクションは並列で実行でき、state rootの計算も同時に行えます。もう列に並んで待つ必要はなく、熱いブロック内でもミームスワップが速く処理される可能性があります。
Efficiency Hacks for Bandwidth and Disk
帯域の無駄遣い?現状のgossipプロトコルはデータを約8倍に増幅しています。対策としては、GossipSub v2(アナウンスしてからデータをプルする方式)やerasure coding(データをシャードに分けて再構築する方式)を使って、より少ないバイト数でブロックを迅速に伝播させる案があります。
ディスク面では、access listsを使ってステートロードをバッチ化し、一括でプリフェッチすることでストールを減らします。買い物リストを持って一度でまとめて買うようなイメージです。
The Long Game: ZKVM and Beyond
先を見据えると、リアルタイムZKVMはデータをblobs(サンプリング可能な安価なデータ可用性)に移し、完全な再実行の代わりに素早い証明チェックに置き換え、stateless validation(全ステートを保存する必要なし)を可能にします。これが実現すれば、すべてのリソースを最適化し、ミームトークンのやり取りコストを大幅に削減する可能性があります。
ただし注意点もあります:L1をスケールさせる過程で、ウォレットなどのアプリが頼るRPCノード、履歴/ステートの成長、同期時間、コンセンサスレイヤー(CL)の堅牢性は維持する必要があります。
ガバナンス面では、スケーリング、blobs、UXに焦点を当てたよりスムーズなフォークを期待できます。EIP-7870はテスト用の「最低限のマシン」基準を定めています。
Why This Matters for Meme Tokens
ミームトークンの世界では、盛り上がりが一晩でアクティビティを急増させることがよくあります。これらのアップグレードはゲームチェンジャーになり得ます。より安く、より速いL1は、Layer 2s に完全依存せずともチェーン上での楽しみを増やします—シームレスなエアドロップ、コミュニティ投票、トークンに紐づいたNFTミントなどがその例です。さらに、自分でノードを動かせるアクセス性を保つことで、ミームコミュニティが愛する分散性も維持されます。
全文を知りたい方は、Ansgar Dietrichsの講演をYouTubeで、あるいはToniの元スレッドをXでチェックしてください。
Meme Insiderでは、次のミームブームに燃料を注ぐブロックチェーン技術の進化を引き続き追っていきます。あなたはどう思いますか—ZKVMが究極のミーム促進装置になるでしょうか?下に感想をどうぞ!