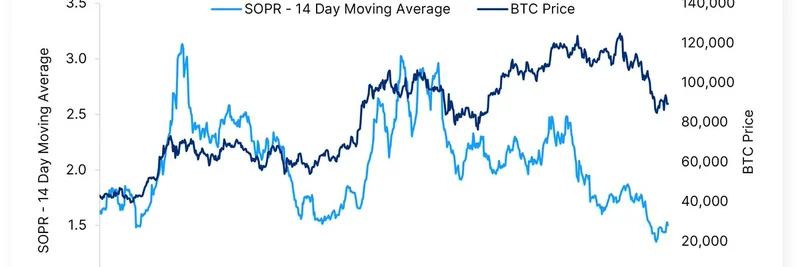ミームトークンがソーシャルメディアの話題とともに上がり下がりする暗号の世界では、クリエイターが実際にどのように収益を上げているかを理解することが重要だ。最近、Xのプロダクト責任者でテック業界のベテランであるNikita Bierの投稿が、このテーマに光を当てた。Bierのoriginal postは、インフルエンサーを目指す人々に対して、クリエイター収益分配やミームコインでの短期的な勝利を追いかけるよりも、日々の見識を共有して専門性を築くことを勧めるもので、コンテンツ制作における長期的視点を促す呼びかけだ。
BlockworksのHead of ResearchであるRyan Connorは、よくあるナラティブを切り崩す鋭いresponseで応じた。彼は、デジタルアートのミントや販売で人気のプロトコルであるZoraや、クリエイターの権限回復を主張するChris Dixon("Read Write Own"の著者)のようなフレーミングが重要な点を見落としていると指摘する。実際には、クリエイターはコンテンツからの直接的な支払いをそのまま懐に入れるだけではなく、間接的に収益化しているというのだ。
考えてみてほしい。トップクリエイターはオーディエンスを獲得するために、スレッドや動画、ミームなど最高のコンテンツを無料で提供する。その後で、ブランドグッズ、講演、スポンサー契約、あるいは自分のプロジェクトを立ち上げるなどの副業で収益を得る。ミームトークンの領域ではこれが特に顕著だ。クリエイターがXでバイラル投稿をして新しいトークンを盛り上げ、買いたいコミュニティを引き寄せる。実際の大きな収益は、トークン供給の一部を保有していることやコミュニティからの寄付などから得られることが多く、必ずしもプラットフォーム手数料からではない。
Connorは、従来型のアプリが「利益の100%を持っていく」という考え方は誤解を招くと指摘する。もしクリエイターが正当な取り分を得られていなければ、彼らは続けないだろう。成功したミームトークンのローンチを見れば分かる:クリエイターは間接的な報酬――ソーシャルキャピタル、パートナーシップ、そして時には大きなトークンの利益――が見込めるため、コンテンツを出し続ける。Time.funのKawzのようなユーザーの返信にもある通り、焦点は直接的な取り分にこだわるよりも、ファンにクリエイターの成功への「参加権」を与えることにある。
ミームトークンに取り組むブロックチェーンの実務者にとって、この視点は大きな転換点になり得る。直接的な収益化を約束するプロトコル(しばしば高いガス代や複雑さを伴う)に固執するのではなく、まずはブランドを築け。トークンの仕組みや市場動向、あるいはミームの文化的側面に関する意外な洞察を共有し続ければ、Bierが示唆するように時間をかけて頼りにされる専門家になれる。そうなればプロジェクトからのスポンサーや、自分のミームコインを既存のファンベースとともに立ち上げる機会が開ける。
この議論は、Xのようなプラットフォームが暗号の物語の中心になりつつある理由を強調している。価値ある継続的なコンテンツにアルゴリズムが後押しをする今、ミームコインの急騰だけに頼らずともオーディエンスを拡大するのは以前より容易だ。ただし暗号の世界では何も保証されないため、飛び込む前には常にDYOR(do your own research)を忘れないこと。
ミーム分野で構築しているなら、これらのプロから学んでほしい:価値の創造に集中すれば、収益化は予想もしない形で後からついてくる。