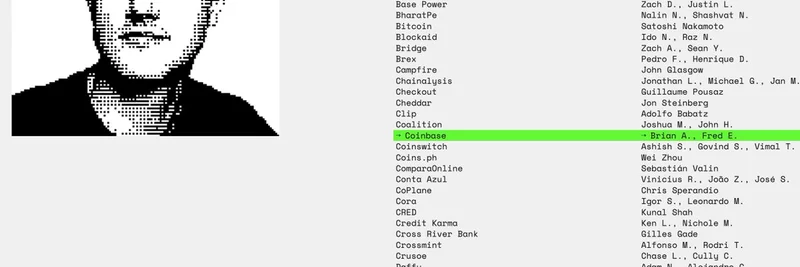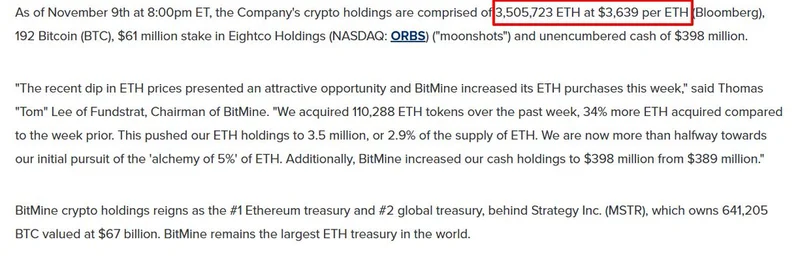最近、暗号ジャーナリストのLaura Shinがツイートで、Cyber Capitalの創設者兼CIOであるJustin Bonsをフィーチャーした彼女のUnchainedポッドキャストの挑発的なクリップを取り上げました。この議論は重要な問いを投げかけます:もしLayer 2(L2)ソリューションがユーザー資金の鍵を握っているなら、それは本当に分散化と言えるのか?この話題は、BaseやArbitrumのようなL2プラットフォーム上で多くの人気ミームが低手数料と高速取引を武器に成長しているため、ミームトークンのトレーダーやクリエイターにとって特に重要です。
議論に火をつけたツイート
Laura Shinのツイート(こちらで見る)は、Unchainedポッドキャスト第907回の短いビデオクリップを共有しています。クリップの中で、Bonsはブロックチェーンのセキュリティにおける明確な対比を指摘します:最も「クソ」なLayer 1(L1)ブロックチェーンでさえ、その分散性のために恣意的にユーザー資金を盗むことはできません。しかし、いくつかの大手L2――rollupsのようなEthereumのスケーリングソリューション――には、運営者が資金にアクセスしたり操作したりする理論上の余地を残す中央集権的なコントロールメカニズムが存在する場合があります。Bonsは、この構造が暗号の基本的な約束である「分散化」と「信頼不要性」を裏切る可能性があると主張します。
用語に不慣れな方向けに整理すると、Layer 1はコンセンサスとセキュリティを担うベースのブロックチェーン(例えばEthereum本体)を指します。Layer 2はスケーラビリティ向上のためにその上に構築され、メインチェーン外でトランザクションを処理しつつL1に決済を戻します。rollupsは人気のあるL2の一種で、コスト削減のためにトランザクションを束ねますが、多くは開発者が管理する中央集権的なsequencerやアップグレードキーから始まります。
L2の中央集権性についてのジャスティン・ボンズの主要な見解
「ETH Is Down Bad While Layer 2s Are Ripping: Are L2s Parasitic to Ethereum?」というタイトルのポッドキャスト全編(こちらで聴く)を踏まえ、BonsはRyan BerckmansとEthereumのスケーリング戦略について議論しています。注目すべきポイントは次の通りです:
L2の中央集権リスク:Bonsは多くのL2がトランザクションの順序付けを行う単一のsequencerのような中央集権的コンポーネントに依存していることを批判します。彼は、これらの「コントロールレバー」が資金の窃盗を可能にする可能性があり、完全に分散化されたL1とは異なると指摘します。クリップでは、上位L2が総ロック価値(TVL)の大部分を占めているため、この問題の切迫性が増していると強調しています。
Ethereumのロードマップへの批判:Bonsは、Ethereumがrollup中心のアプローチで「過去に囚われている」と主張します。ブロックチェーントリレンマ(セキュリティ、スケーラビリティ、分散化のバランス)は時代遅れであり、SolanaのようにL2依存を強めずに高スループットを達成している代替案を指摘しています。
L2の寄生的性質:議論では、L2が手数料を獲得することでETHの本来の価値を食い尽くしているのではないか、つまりL1の活動を高めるはずの収益がL2に流れてしまっているのではないかという疑問が投げかけられます。Bonsは、L2のインセンティブが「倒錯している」と示唆し、チームが分散化よりも利益を優先することで恒久的な中央集権化につながる可能性を示します。
比較と予測:BonsはSolanaのロードマップを称賛し、より良いスケーリングの可能性を評価するとともに、L1改善のためにSNARKs(Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge)など未検証の技術に依存するEthereumの方針に疑問を投げかけます。
BerckmansはL2をEthereumのネットワーク効果を高めるものとして擁護しますが、Bonsの懐疑的な見方はユーザーの信頼に影響を与えうる脆弱性を浮き彫りにしています。
ミームトークンにとっての意味
ミームトークンは楽しくもボラティリティの高い暗号界の人気者であり、多くは手数料の安さや速度を求めてL2でローンチされます――Base上のDogecoin風コインやOptimism上でバイラルになったプロジェクトなどを想像してください。しかし、Bonsの指摘が正しければ、この利便性にはリスクが伴います。L2の中央集権的要素は、ハッキングやrug pull、運営者の不正行為にユーザーをさらす可能性があり、「信じるな、検証せよ(Don't trust, verify)」という精神を損ねることになりかねません。
ミームエコシステムに踏み込むブロックチェーン実務者にとって、この議論はデューデリジェンスの重要性を改めて示しています。考慮すべき点:
- 分散化に向かうL2の選定:分散型sequencerを導入するなど、完全分散化に向けて前進しているL2を探す。
- チェーンの分散化:ミームのローンチ先として、L2層を介さず高いTPS(1秒あたりのトランザクション)で迅速な取引をサポートするSolanaのようなL1を検討する。
- 情報収集を怠らない:スケーリングソリューションがどのように進化しているかを追い、ミームトークン戦略が真の分散化と整合しているかを確認する。
ミーム文化が暗号普及を牽引し続ける中で、Bonsのような疑問は、誇大広告の下にあるセキュリティと分散性の重要性を思い出させてくれます。
ミームトークンに興味があり、知識を深めたい方は、当サイトのミームトークンの知識ベースをぜひご覧ください。L2の分散化についてどう思いますか――ゲームチェンジャーか、それとも赤旗(危険信号)か?コメントで教えてください!