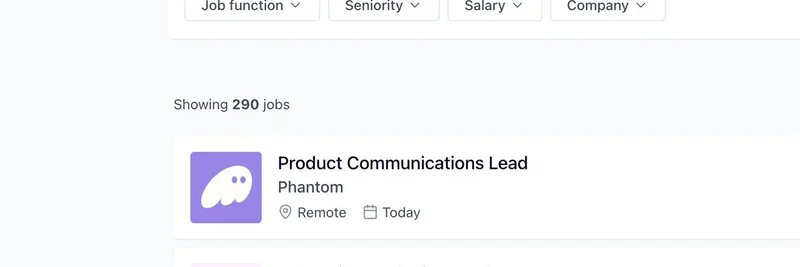もしあなたが暗号通貨やブロックチェーンの分野を追っているなら、a16z(Andreessen Horowitz)が単に次の大きなトークンに資金を出しているだけではないことはご存知でしょう。彼らはAmerican Dynamism(アメリカン・ダイナミズム)など、現実世界に影響を与える技術の未来を形作ることにも深く投資しています。この投資テーマは、防衛から宇宙探査に至るまで、テクノロジーと実世界のインパクトを融合するスタートアップに焦点を当てています。最近、a16zのツイート(link)で「The Ben & Marc Show」ポッドキャストの一部クリップが紹介され、マーク・アンドリーセンがアメリカがいかに製造業の優位性を取り戻せるかを解説しています。これは、愛国的または技術志向の物語に結びついたミームトークンに注目するブロックチェーン関係者にも示唆を与える会話です。
そのクリップで、アンドリーセンはかつてのさびついた工場とは異なる再工業化の姿を描きます。彼は、高度に自動化された工場で先端製品――先進的な自動車、ロボット、AI駆動のハードウェアなど――を生産する飛躍について語ります。「What you have is a large number of jobs that are kind of called them blue-collar-plus jobs(多くの職種がいわゆるブルーカラー・プラスの仕事と呼ばれるようなものになる)」と彼は説明し、手作業と高度な技術スキルを組み合わせた役割を指しています。これは祖父の時代の単純な組み立てラインの仕事ではなく、精巧な機械やシステムの保守を伴う高収入でやりがいのある職です。
彼は実例としてTeslaの工場を挙げます。イーロン・マスクの企業群がどのようにして大規模に電気自動車を量産しているのか疑問に思ったことがあるなら、それは自動化と熟練労働の融合によるものです。アンドリーセンは、将来の製品に注力することで、アメリカは単に雇用を増やすだけでなく、より良い雇用──高賃金で魅力的、そしてイノベーションに直結する仕事──を生み出せると主張します。そして重要なのは、もし米国が本気で取り組まなければ、電話からドローンまで中国がこれらの分野を支配してしまうだろうという点です。
これは、ポッドキャストのより広いエピソード(link)と直接結びついています。そこではa16zのパートナー、Katherine BoyleやDavid UlevitchがErik Torenbergと共にAmerican Dynamismの起源を掘り下げ、シリコンバレーの防衛関連ルーツや、COVIDを契機に物理世界でのモノづくりが再び注目されるようになった変化をたどります。SpaceXが宇宙技術を変革したことから、Andurilが防衛分野の経済性を再考した事例まで、いかにアメリカが作ることによって世界的な優位を保つ必要があるかが強調されます。
ブロックチェーン関係者にとって、これは単なる製造業の話以上の意味を持ちます。分散型技術はこの再工業化で大きな役割を果たし得ます。資産のトークン化はこれら先端工場への資金調達手段になり得るし、NFTsやmeme tokensはアメリカ製イノベーションを支持するコミュニティを結集する手段になり得ます。スマートコントラクトはこれら「未来の製品」のサプライチェーンを効率化するかもしれません。ジョーク扱いされがちなミームトークンですら、資金と注目を動員できることが証明されています――American Dynamismをテーマにしたトークンが、防衛や自動化のスタートアップを後押しする未来を想像してみてください。
アンドリーセンは、規制改革と安価なエネルギー(原子力やブロックチェーンで最適化されたグリッドに支えられた再生可能エネルギーなど)がなければ競争に負けると警告します。しかし彼は、21世紀のアメリカにとって「驚くべき物語」があると見ています:昨日の製品ではなく明日の技術を作るための再工業化です。これは、迅速に構築し世界規模でスケールすることが求められる暗号界に響く行動喚起でもあります。
もしあなたがブロックチェーンの実務者やミームトークン愛好者なら、このクリップは次の大きな波が単にデジタルなものだけではなく、暗号が物理世界と交差する領域にあるかもしれないことを思い出させてくれます。より深掘りしたいならポッドキャスト本編をチェックし、a16zの投資がどのようにこれらのギャップを埋めているかに注目してください。次のホットなミームトークンは「ブルーカラー・プラス」な雰囲気を全面に出すものかもしれません。