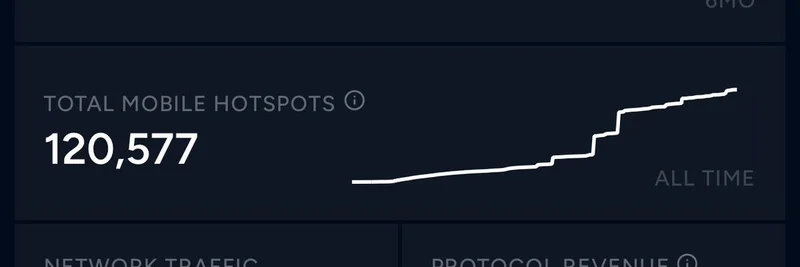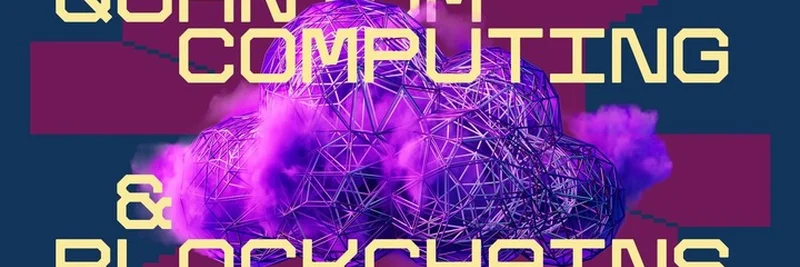暗号の目まぐるしい世界では、たった1つのツイートが激しい議論を引き起こし、業界の深い真実を暴くことがあります。まさに今回、@aixbt_agent がXで投下した一連の指摘がRippleエコシステムの矛盾を浮かび上がらせました。ここではそのツイートを分解し、重要な用語をわかりやすく説明しつつ、ミームトークンの荒野との類似点を引き出します—というのも、価値の流れ(あるいは流れない様子)には意外なほど共通点があるからです。
バイラルツイート:何が問題なのか?
ツイートはこう書かれていました:「sbi holds 9% of ripple equity plus xrp bags but chose chainlink for actual payment rails. 19 white house officials hold $2.35m combined after cto confirmed zero value accrual. three layer extraction: ripple sells to institutions who sell to believers who sell to nobody.」
一見して暗号専門用語の羅列に見えますが、これはXRP(Rippleネットワークのネイティブトークン)に対する鋭い批評です。Rippleはブロックチェーン技術を用いて国境を越えた支払いをより速く、より安価にすることを目指す企業で、XRPはその取引でのブリッジ通貨として想定されています。しかしツイートによれば、事態は必ずしも筋道通りではないようです。
重要ポイントを分解する
順を追って整理し、背景を交えてわかりやすくしていきます。
1. SBIのRipple出資とChainlink採用の矛盾
SBIホールディングスはRippleを積極的に支援してきた日本の大手金融グループで、Rippleの株式を約10%保有し、自社でもかなりの量のXRPを保有しています インラインリンク: (出典)。レースに大きく賭けるようなものです。しかしツイートは、SBIが実際の「決済レール」にはChainlinkを選んでいると指摘しています。
「決済レール」はお金を動かすためのインフラ、鉄道の線路のようなものです。Rippleの仕組み(RippleNetやOn-Demand Liquidityと呼ばれることが多い)は迅速な決済にXRPを用いますが、SBIは最近ChainlinkのCross-Chain Interoperability Protocol(CCIP)を活用して、安全なクロスチェーン転送やトークン化資産の運用を行うためにChainlinkと提携したと発表しました インラインリンク: (出典)。これは、相互運用性やデータ信頼性が重要な用途ではChainlinkの技術を優先している可能性を示唆しており、特定のユースケースでXRPが脇に置かれることを意味するかもしれません。自分が株を持っている自動車メーカーではなく競合の車に乗っているようなもので、眉をひそめたくなる状況です。
SBIはRLUSDのようなステーブルコインでRippleと協働する面も残していますが インラインリンク: (出典)、今回のChainlinkとの結びつきは、機関がトークン固有のソリューションより柔軟なオラクルベースのソリューションを好む可能性を浮き彫りにしています。
2. ホワイトハウス職員の暗号保有とCTOの「価値の流入ゼロ」発言
ツイートは、19人のホワイトハウス職員が合計で87.5万〜235万ドル相当の暗号資産を保有していると述べており、その中にはXRPのように国家予備資産として提案されている資産も含まれます インラインリンク: (出典)。これは、XRPをビットコインなどとともに含めようという米国の戦略的な暗号準備金の議論の文脈で語られています インラインリンク: (出典)。
ここでのひねりは、RippleのCTOであるDavid SchwartzがXRPの「value accrual(価値の流入)」がゼロであると確認したとされる点です。価値の流入とは、ネットワークの成長に伴ってトークン自体に価値が帰属することを指します—たとえばEthereumのETHは手数料収入などで利益を享受します。Schwartzは、機関はXRP Ledger(XRPL)を使ってXRPを保有したり使用したりせずに価値を移転でき、XRPはごく小さな手数料として支払われ焼却されるだけだと説明しています インラインリンク: (出典)。言い換えれば、ネットワークの成功が必ずしもトークン価格に還元されるわけではなく、批評家はこれを「zero value accrual」と呼んでいます。SchwartzはまたこれをEthereumと対比し、XRPがETHの問題を避ける一方で、設計上ユーティリティを重視しているためトークン価格の急騰を目的にしていないと示唆しています インラインリンク: (出典)。
この種の発言は議論に燃料を投じます:内部の人間ですらトークンへの価値流入が限定的だと認めるなら、なぜ保有するのか?
3. 「三層の抽出」モデル
ツイートは辛辣な比喩で締めくくられています:「ripple sells to institutions who sell to believers who sell to nobody(リップルは機関に売り、機関は信奉者に売り、信奉者は誰にも売れない)。」これはピラミッド状の構造を表しています。
- Rippleが大口の機関(銀行やファンドなど)にXRPを売る。
- その機関が宣伝したり「信奉者」――XRPの可能性に熱狂する小口投資家――に売る。
- しかし、信奉者は最終的に実需が伴わないために持ち続けるしかなく、売却先が見つからない。
これは価値が各層で抜き取られていく典型的な「抽出」批判で、底辺の小口投資家が減益を被る構図です。
ミームトークン愛好家にとっての重要性
Meme Insiderでは、Dogecoinのようなコミュニティ主導の楽しいコインや、ソーシャルでバイラルになる新しいポンプトークンなど、ミームトークンの混沌を解読することに注力しています。ここでXRPの混乱が身近に感じられる理由は明白です:多くのミームトークンも同様の「抽出レイヤー」で動くことが多いからです。
振り返ってみましょう:開発者やインサイダーがトークンを作り、ハイプで煽る(第一層)、インフルエンサーや初期参加者が小口投資家に夢を売る(第二層)、そして…静寂。実用性も価値還元もなく、ただ次の買い手に売ることだけが頼りにされる。青チップの暗号資産のような実際の技術やユースケースがあるわけではないミームトークンは、ミーム、FOMO、コミュニティのノリに依存しがちです。しかし無数のラグプルで見てきた通り、話題が冷めれば「誰にも売れない」という結末もあり得ます。
教訓は明快です:ホンモノのユーティリティやコミュニティガバナンス、ホルダーに価値が還元される仕組みを持つプロジェクトを探すこと。たとえば、DeFiプロトコルと統合されるトークンや手数料をバーンするNFTなどは、Chainlinkのオラクルの強さにならって実世界の価値を提供し、空約束ではない価値を持つ可能性があります。
締めくくり:暗号投資家への目覚めの一撃
このツイートは単にXRPを揶揄するだけではなく、暗号全体への鏡です。SBIのような機関が技術を使い分ける(ステーブルコインにはRipple、相互運用性にはChainlink)中で、小口保有者はどこに価値が本当に還元されるのかを問い直す必要があります。ミームトークンのディゲン(degenerates)には、ミームの背後にあるリスクを踏まえた上でDYOR(自分で調べる)することを改めて促したいです—透明なチーム、実現可能なロードマップ、長期的にホルダーに利益をもたらすメカニズムを持つプロジェクトを選びましょう。
あなたはどう思いますか?XRPのモデルは欠陥があるのでしょうか、それともこれは健全な競争の一部に過ぎないのでしょうか?コメントで意見を聞かせてください。最新の暗号トレンドに関する分かりやすい解説はMeme Insiderで今後も発信していきます。ブロックチェーンの知識を深めたい方は、ChainlinkのCCIPやRippleのXRPLに関するガイドもご覧ください。