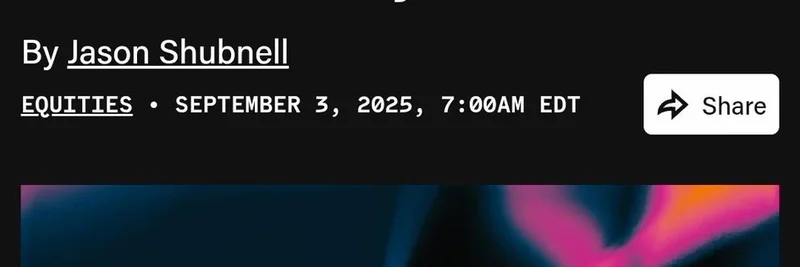Solanaは「ただのミームコインばかり」と揶揄されることがあるが、Galaxy HQでDeFi責任者を務めるMarc Antonioはそうは見ていない。最近のtweetで彼は見方を覆し、数十億ドル規模のミームコイン取引は脇役ではなく、Solanaを世界規模の証券対応に備えさせるための本格的なストレステストだったと主張している。
話を分解しよう。ミームコイン(ミームに由来する、Dogecoinのような、あるいは最近のSolanaベースのヒット作)は、主にインターネット上でバイラルになる楽しい暗号通貨で、激しい価格変動と莫大な取引量で知られている。こうした取引はどのブロックチェーンでも限界を試すことになる。スケーラビリティを念頭に置いて設計された高性能ブロックチェーンであるSolanaは、こうした混乱の舞台になってきた。
MarcはHelius.devのMertによる投稿「Internet capital markets」を引用しており、そこにはGalaxy DigitalがSEC登録株式をSolana上でトークン化する計画に関する記事の見出しが添えられている。ここでのトークン化とは、会社の株式のような実世界資産(RWAs)をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換し、取引や所有を容易にすることを指す。
Galaxy Digitalのこの動きは、Solanaが実世界でのユースケースへとシフトしていることを示している。しかし、なぜミームコインなのか?Marcが指摘するように、ミームコイン取引による膨大なボリューム―数十億ドルが高速で回転する様子―はSolanaの「market rails」(市場を支えるインフラ)を試した。これはオーダーブック(order books)、流動性プール(liquidity pools)、トランザクション処理など、取引を扱うインフラ全般を指す暗号業界の言い回しだ。
同様のプレッシャーでへこたれる可能性のある他のブロックチェーンとは異なり、Solanaは並列処理と高スループットという独自のアーキテクチャのおかげで耐え抜いた。この耐久性は単なる自慢話ではなく実務的意味を持つ。つまり、従来の金融大手が大規模に資産をトークン化し始めたときに、Solanaが実戦で試されているということだ。Mertが言うところの「internet capital markets」――シームレスでグローバルなオンライン取引プラットフォーム――の土台になりうる。
もちろん、全員が賛成しているわけではない。ツイートへの返信には、$TRUMP や $PENGU といったトークンがネットワークの問題なくローンチされたことを挙げる賛同者もいれば、「copium(現実逃避)」と批判したり、Solanaを「詐欺まみれのcrime chain」と呼ぶ懐疑派もいる。しかしそれが暗号の世界だ――熱い議論がイノベーションを駆動する。
Meme Insiderでは、こうしたトレンドを解きほぐすことに注力している。ミームトークンやブロックチェーン技術の広がりに飛び込むなら、ミームコインの遊び場から証券対応の基盤へと進化するSolanaを理解することが有利になるだろう。RWAsには注目しておこう。従来の金融と暗号を橋渡しし、市場を再定義する可能性がある。
あなたはどう思う?Solanaはミームの枠を超えて実力を示したと思うか?コメントで意見を聞かせるか、Solanaの最新動向をチェックしてみてほしい。