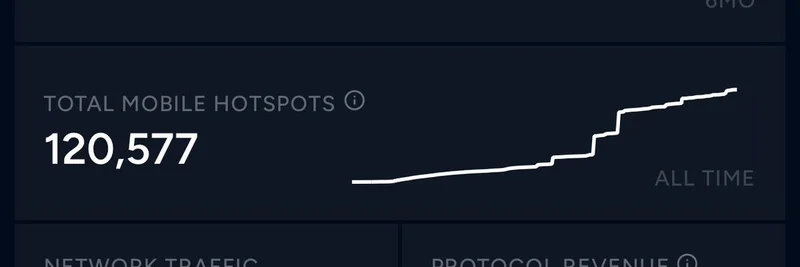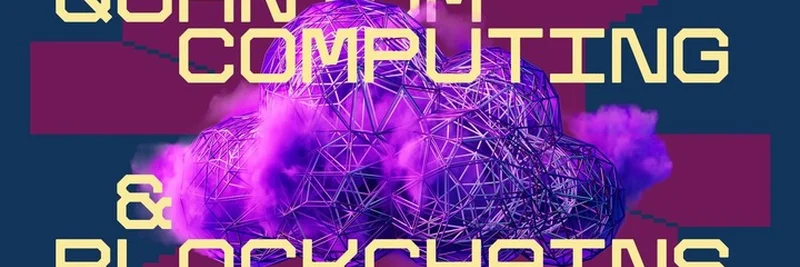急速に進化する暗号資産の世界では、real-world assets(RWAs)が従来のコレクティブルとデジタル取引の橋渡しをしています。X上での@defi_monkによる最近のスレッドはこの話題に火をつけ、我々が小麦や大豆のようなコモディティを物理的に触らずに取引していることを指摘しました。ならば、なぜコレクティブルにも同じことを適用しないのでしょうか?ブロックチェーン愛好者やミームトークンのファンにとって、これが何を意味するのか見ていきましょう。
核心はシンプルです:エキゾチックなRWAsのために特化したカストディアン(管理者)として機能するプロトコルを作ること。RWAsを実物のデジタル表現、つまりトークン化された実世界アイテムと考えてください。保管や輸送の手間なく、ブロックチェーン上で購入・販売・取引できるデジタルな表現です。@defi_monkはこれがポケモンカードに限定される必要はないと指摘していますが、ユーザーに強く刺さるプロダクト・マーケット・フィット(PMF)を達成するための絶好の出発点になると述べています。
なぜポケモンなのか?それは「ガチャのドーパミン」、不確実性と報酬のスリルに尽きます。日本のガチャでレアを引き当てる感覚に近いものです。暗号の文脈では、トークン化されたコレクティブルを投機の対象にし、より良い結果を狙って再挑戦し、バズから利益を得ることに相当します。ある返信が指摘するように、流動性の低いこうした資産のフラクショナル所有はまだ発展途上ですが、避けられない流れに思え、高価な品を一般トレーダーにも開放する可能性があります。
議論はすぐに広がりました。ユーザーからはLabubuのフィギュアやスニーカー、腕時計のようなアイテム向けプラットフォーム構想が寄せられました。例えば@Pratik_in_Web3は、ポケモン等を1年以上取り扱っているプラットフォームのBeezieを挙げています。他の参加者は、多くのトレーダーは実物のカードを求めているわけではなく、ノスタルジーに包まれたソフトギャンブルとしての投機が目的だと強調しました。
これはミームトークンのエコシステムにも自然に結びつきます。コミュニティ駆動の盛り上がりやバイラルなトレンドが価値を生み出す場面で、トークン化されたポケモンのレアや他のコレクティブルを担保にしたミームコインを想像してみてください。楽しさと金融が混ざり合い、物理的な手間なしにコレクターの高揚感を掴めます。@0xKeefが言うように、人々は箱を蓄積したいのではなく、カードで投機したりレアを追いかけたりしたいのです。
もちろん、カストディ(誰が実物を保管するのか)などのハードルはありますが、ポテンシャルは大きいです。こうしたプロトコルは、従来は大手が支配していた市場へのアクセスを民主化する可能性があり、DeFi(分散型金融)が貸借市場を開放したのと似た役割を果たし得ます。
ミームトークンに関心があるなら、遊び心のあるテーマとRWAsを融合するプロジェクトに注目してください。単なる取引ではなく、そのドーパミン体験を取り込みつつ、より包摂的なブロックチェーン経済を築く試みです。次のポケモンの引きをデジタルで取引する準備はできていますか?