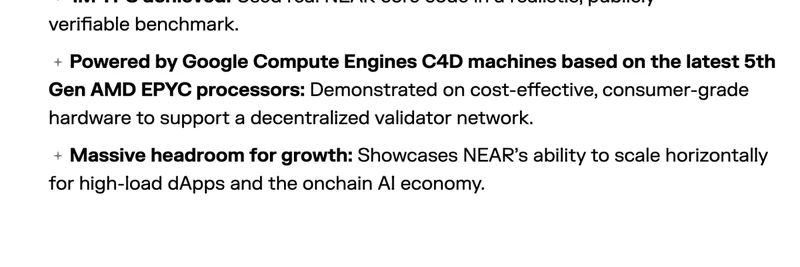急速に進化する分散型金融(DeFi)の世界では、セキュリティ侵害が一夜にしてプロトコルの命運を左右します。最近、@officer_cia のツイートが暗号コミュニティを揺るがし、BNB Chain上の人気レンディングプラットフォームであるVenus Protocolが5億ドルもの顧客資金を巧妙なハックに晒していたと主張しました。さらに、問題を塞いだ研究者に約束していた100万ドルのバウンティの支払いを拒否したとも報じられています。もしこれが事実なら、DeFiレンディングプラットフォームへの信頼を大きく揺るがし、バグバウンティ制度の継続的な問題点を浮き彫りにするでしょう。
順を追って説明します。Venus Protocolはユーザーが暗号通貨を貸し借りできるプラットフォームで、伝統的な銀行のような機能をブロックチェーン上で提供します。ネイティブトークンのXVSはガバナンスや一部では担保として重要な役割を果たします。ツイートによれば、この脆弱性は数年前の悪名高いMango DAO exploitと非常によく似ていたとされています。その事件では、攻撃者が価格を操作してプロトコルから資金を引き出しました。
報告されているVenusの攻撃の仕組みは次の通りです。攻撃者は市場で約500万ドル相当のXVSを蓄積し、供給を囲い込むことを狙いました。十分な支配を得た後、そのXVSをVenusに担保として預けます。次に、Binanceのような取引所で大規模な買いを入れて価格を急騰させ、プロトコルの価格を決定するoracles(価格フィード)により担保価値を人工的に膨らませます。この操作により担保が10億ドル超に見えるようになり、プロトコルのTVL(Total Value Locked)を実質的に全て借り出して引き出すことが可能になります。
Mango DAOとの主要な違いは何か?Mangoのケースではフューチャーズのヘッジを使った仕組みが絡んでいましたが、今回のVenusの事例は純粋にスポット市場での操作によるレンディングプラットフォーム狙いでした。デリバティブは使わず、流動性の低い資産をそのまま操作する手口です。これは、oracles操作や低流動性トークンがどれほどDeFiに脆弱性をもたらすかを思い起こさせます。特に、熱狂で価格が乱高下しやすいmeme tokenの世界ではこうしたリスクが顕在化しやすいです。
ツイートは、あるセキュリティ研究者がこの進行中の攻撃を発見してVenusチームに警告し、結果的に5億ドルのユーザ資金を救った可能性があると主張しています。報酬としてVenusはバグバウンティプログラムを通じて100万ドルを約束したが、問題解決後にそれを撤回したと伝えられています。こうした話は暗号業界では珍しいものではなく、Curve Financeなどのプロジェクトでもバウンティを巡る争いが起きていますが、これは説明責任の重大な問題を提起します。プロトコルが約束を守らないなら、研究者が脆弱性を報告する動機はどこにあるのでしょうか。
meme tokenに関心のある人には身近な問題です。多くのmemeコインは同様に低流動性の環境で運用されており、こうした攻撃の格好の標的になります。VenusのXVSは純粋なmeme tokenではないものの、コミュニティ主導の熱狂やボラティリティといった特徴を共有しており、リスクを増幅させる可能性があります。レンディングプラットフォームでmeme tokenを保有・取引しているなら、分散やプロトコルのセキュリティ監査に注意を払うべきだという警鐘です。
暗号の世界が進化するにつれて、複数のデータソースを用いるなどのより強固なoracle設計や、透明性のあるバウンティプロセスの必要性が強調されます。Venus Protocolの返答を注視しており、早急に状況を明らかにしてくれることを期待します。その間、DeFiに飛び込む際は常に自分でリサーチを行い、実績のあるプラットフォームを検討してください。
皆さんはどう思いますか?これはVenusにとって大きな赤旗ですか、それとも暗号業界の日常の一幕に過ぎませんか?下のコメントで意見を聞かせてください。