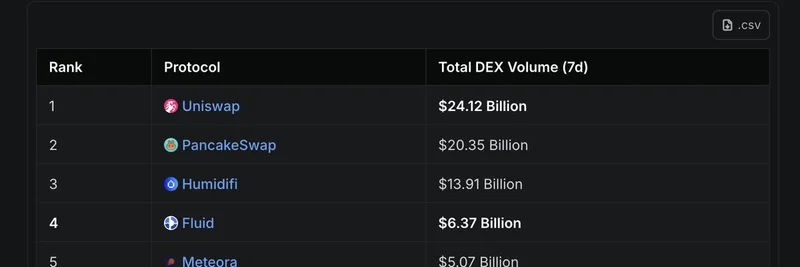目まぐるしい暗号通貨の世界では、エアドロップはプロジェクトがトークンを配布しコミュニティの盛り上がりを作るための定番手法になっている。しかし、最近の@ashen_oneによるXのスレッドが指摘するように、受領者が売らないだろうと期待するのはただの願望に過ぎない。これを分解して、成功したいミームトークンチームにとって何を意味するのか見てみよう。
エアドロップは本質的に「無料の金配り」だ――プロトコルと何らかの形で関わったユーザーにトークンが配られる仕組みで、staking や取引などの行為でポイントを稼ぎ、そのポイントをトークンと交換する形がよくある。問題は? ほとんどの人がまさに換金を目的にこうしたポイントをファーミングするということだ。数ドルしか持たない小口保有者であれ、何百万も持つホエールであれ、動機は利益だ。@ashen_one が指摘する通り、初期投資家だって最終的な利益を見越して大金を投じている。
ポイントシステムが長期間続けば続くほど(例えば6ヶ月以上)、即時ダンプの可能性は高くなる。なぜならファーマーは時間や場合によっては資本を投下しており、「無料の金」を見逃すはずがないからだ。クレジットカードのリワードを貯めているのと同じで、もちろん換えるだろう。ボラティリティが支配するミームトークン界隈では、新しいトークンを持ち続けることは、すぐに利益を確定できる機会と比べてリスクに感じられる。
これは悪意の問題ではなく、機会の多い市場での合理的な行動だ。ファーマーを責めても本質は変わらない:プロジェクト側がこれを予測して対策を立てる必要がある。深いユーティリティではなくバイラルな勢いに頼ることが多いミームトークンでは、売り圧力を放置すると価格は素早く暴落し、ハイプがラグプルっぽい雰囲気に変わってしまう。
では、チームはどう対抗すべきか? @ashen_one は staking rewards、buybacks、token burns といったツールを提案している。だが、これらは市場に流れ込むトークンの洪水に対抗できるだけの十分な強度が必要だ。例えば Ember Protocol は、ダンプを最小限に抑えるための独自のトークン設計で常識を覆している。配布方法の革新がローンチの成否を左右する、という良い教訓だ。
Jupiter や Hyperliquid のような成功例を見てみよう。これらのエアドロップが成功した理由は:
- レトロアクティブ(過去の利用者への還元)で、既に信頼できるプロダクトを利用していたユーザーに報いたこと。
- ローンチ後もトークンに価値が残り、プロジェクトの継続的な成長がホルダーの関与を維持したこと。
ゼロにするような大暴落はなく、むしろ持ち続けることが魅力になる安定したパフォーマンスがあったのだ。対照的に、多くのエアドロップが鳴りを潜めるのは、その基盤が欠けているからだ――刺さるプロダクトも、残り続ける理由もない。
結局のところ、大きなエアドロップを売らずに持ち続けるのは、ほんの一握りの熱狂的な支持者やリスクを取る人々だけだ。ミームトークンを作る側が取るべき鍵は、短期的な転売欲を上回る本物の価値を生み出すことだ。ファーマーを理解し、売り圧力を和らげる仕組みを構築し、市場がダンプしたくなくなるだけの十分な理由を与える。そうすれば、エアドロップを一時的なギミックから持続的な成功への踏み台へと変えられる。