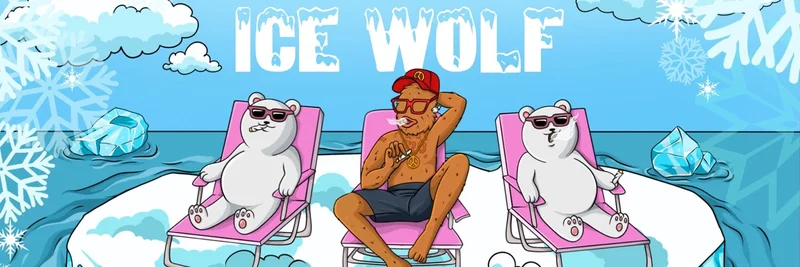暗号通貨の世界では、トレンドがポンプ&ダンプよりも速く変わることもしばしばだ。そんな中、X(旧Twitter)に投稿されたあるスレッドがトレーダーや愛好家の間で活発な議論を巻き起こしている。自己紹介で「semi-retarded trader」と名乗る@The__Solstice が投稿したそのスレッドは、ミームコインがなぜ盛り上がるのか、あるいはしぼんでしまうのか――その本質を掘り下げている。鍵となるのは「信念」、あるいはその欠如であり、それが2025年Q4の大局にどう影響するかが論点だ。
スレッドは、$ASTER と $WIFI のChief Meme Officerである@SpottieWiFi の投稿を引用する形で始まる。SpottieWiFiの元投稿は、パフォーマンスの悪いトークンをホールドしている「shit bags」を揶揄しており、彼らが最後のポンプを待ち望み、真剣な資金で$ASTERに飛び込もうとしていると嘲る内容だ。彼は$ASTERが10ドル以上に跳ね上がると予想し、皮肉めいたサムズアップも添えている。
@The__Solsticeは次のように応答する: 「ミームの核心的教義、というかその欠如が問題なんだ。誰も信じなければ魔法は起きない。Q4は上げだが、perps dexes と stablecoin alts のみだ。なぜなら人々は本気でそれらが数十億になり得ると信じているからだ。で、実際そうなる。そして我々は一度、ついにまた裕福になるんだ。」
ここで言う "perps dexes" は、満期のない永久先物契約を専門に扱う分散型取引所を指す――満期のないレバレッジ取引と考えれば分かりやすい。stablecoin alts は、USDTやUSDCのような大手以外の代替ステーブルコインで、ドルペッグながら独自のひねりを持つものが多い。重要なのは?これらの分野は巨大な時価総額に到達し得るというコミュニティの強い信念があるという点で、ミームコインの多くのように熱が急速に冷めてしまうリスクが相対的に低いことだ。
返信は次々と寄せられ、暗号コミュニティ内の意見の分裂を反映している。@Gorni_og は「good tech like $WURK will help」と書き、しっかりした技術が特定のプロジェクトへの信頼を支え得ると示唆する。
@G00Dw1ll は「そうだ。ミームが増えれば増えるほど、個々のミームに対する関心は薄れる」と付け加えた。これはミームコイン領域の飽和問題――選択肢が多すぎて注目も信念も希薄化する、という指摘だ。
SpottieWiFi本人もGIF付きで力強く「YES」と返し、Doctor Strangeの「We're in the endgame now(今がエンドゲームだ)」という場面のGIFを添えてミーム時代が変化またはピークに達している可能性を示唆した。
別のユーザー、@ElinaWeb3 は端的にこう述べる:「信念が魔法を生む」。
@DCTradez08_ は「RETURN TO MEMES!(ミームに戻れ!)」と叫ぶが、@The__Solstice は冷ややかに返す:「貧乏のままでいたいなら、どうぞ」。強烈な一撃だ――色あせたミームにしがみつく者たちへの直球の皮肉だ。
@ToesBeaver はこう提案する:「Q4はアニマルメタかもしれない—Hugoは本気のプレイになるかも…」と、動物テーマのミームを示唆。ピグミーカバの子どもの命名投票で「Hugo」が先行しているスクリーンショットも添えられている。
@KiloTNT_ は「コーギー買えよ、兄弟」と可愛いコーギーのGIFを添えて軽口を叩く。
@tVC16z は苛立ちを表してこう言う:「ミームがクラッシュして燃え尽きればいいのに」。
最後に @JackN1x がバランスの取れた見解を示す:「ミームは群衆を引きつけるが、rails(基盤)が乗り物を支える。Q4の熱狂は実際の流動性がなければ消えるし、リスク管理はドーパミン的な資金ではなく耐久性を築くためにある」。
このスレッドはCrypto Twitterの今をよく捉えている:DeFiやstablecoinへの楽観、飽和したミームに対する懐疑、そして信念こそが秘密のソースであるという再確認。2025年Q4に向けて、$ASTER のようなプロジェクトはコミュニティのハイプに賭けているが、@The__Solstice が指摘するように、本物の確信があれば適切なアルトは何十億という時価総額に到達し得る。
先を行きたいブロックチェーン実務家にとって、こうしたスレッドは金の情報だ。ミーム領域ではテクノロジー単体よりもセンチメントが市場を動かすことが多いことを示している。もしあなたがミームをホールドしているなら、自問してほしい:コミュニティは本当に信じているか?
全文のスレッドはここで確認できる:here。議論に参加しよう。