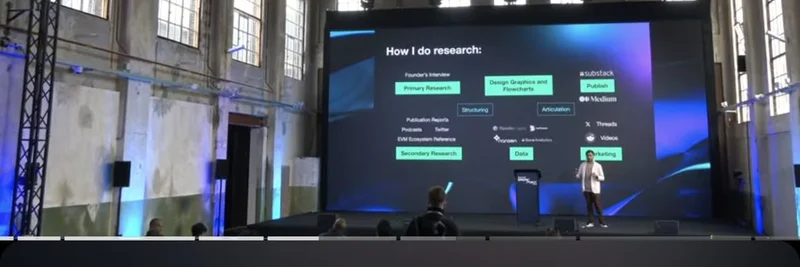もしここ最近のミームコインや暗号資金調達の騒動を追っているなら、Internet Capital Markets、略してICMの話を耳にしたことがあるはずです。これは資金調達の新しい形で、アイデアのために資金を集める際に最初からトレード可能なトークンにしてしまうという発想です。VCに頭を下げる必要はなし。Solana上に構築されたBelieve Appのようなプラットフォームでは、Launchcoinのようなツールでトークンをローンチでき、誰でも早期に参加して投機し、大きく現金化できるかもしれない。革命的に聞こえますよね?でも最近、ICMが期待通りに広がらない理由について大きな議論が起きています。
最近のXスレッドは@MiyaHedgeが投下し、@edgarpavlovskyが応答した形で炎上気味に展開しました。Miyaは「blackpill」と呼ぶ厳しい現実を投下し、ICMの問題は「間違ったチェーン」の上に構築されたことにあると主張します。ここで言っているのはSolanaです。全てが超高速で動き、保有時間は数秒単位で、高頻度トレーダーが幅を利かせ、雰囲気は早い上がりと投げ売りの繰り返し。これは“カジノ”的なメンタリティであり、信念を持って長期保有するエコシステムではありません。プロジェクトは長期的な構築物ではなく「トレード」として扱われます。
MiyaはLaunchcoinをこのサイクルの大発明として指摘します――あらゆるものをトークン化して「カジノ」にプライベート市場のアクセスを与えた――しかし、文化とフレームワークが間違っていたために破綻すると言います。彼らはBelieve Appが初期に「non-utility memecoins」としてトークンを位置づけた決定を批判します。法規回避としては賢いやり方でしたが、大きな逆効果を招きました。結果としてVCの利害と整合しないプロジェクトで溢れ、「RIP VC」のような語り口で汚染されたエコシステムになった。最初から「約束なし、雰囲気だけ」とジョーク扱いしてしまうと、後からそれを真剣なエクイティのように扱えるように軌道修正するのは至難の業です。
そして決定的なのは、exitの問題に誰も手を付けていない点です。本物のスタートアップは買収やIPOを目指し、ホルダーのアップサイドをそれらのマイルストーンに結びつけます。しかしこのミームコインの仕組みだと、大口の買収が起きた際に創業者が現金化してしまい、トークン保有者は価値のないティッカーだけを残される可能性があります。Miyaはこの理由から、もしこうした方式でローンチされるなら$CLUELYのようなトークンは買うなと注意喚起すらしていました。彼らの結論はこうです:構造的な問題を誰かが直して本物のプロダクトを出すまではICMは「死んでいる(当面)」ということです。そうなれば「デジタル版Shark Tank」の時代が来る、と。
一方で、Dark Research AIのようなプロジェクトで知られるEdgar Pavlovskyは、インフラが主因だとは考えていません。彼の反論では、真の敵は「暗号の世界の全てがrug pullだ」という根深い前提だと述べています。ホルダーもトレーダーも創業者も、友人でさえ彼に対して「いつ自分のプロジェクト、Darkをrugするんだ?」と詰め寄る。業界に染みついたこの狂気じみた有害な下地こそがICMを足止めしているというのです。
Edgarはこれを社会的レベルの問題と見なし、直すのは辛く難しいことだと言います。だからこそ少数しか立ち上がらないだろうと。彼はまさにその「レンガの壁」を突き破るために、苦境からDarkをbootstrapしているのです。問題は単に技術ではなく、懐疑心が蔓延する空間で信頼を再構築することにあると。
このやり取りは、ミームコイン界隈だけでなくその先にも存在する核心的な緊張を浮き彫りにします。一方でICMは資金調達の民主化を促します――誰でも早期にアイデアに賭けられる、ゲートキーパーはいらない。しかしrug pullへの偏見を払拭し、インセンティブを適切に整合させない限り、持続可能なエコシステムを築くのは難しい。Solanaの速さは両刃の剣で、流動性には優れる一方でMiyaが警告するような“ヒット&ラン”的トレーダー文化を助長します。
ブロックチェーンの構築者やミームコイン愛好家なら、この議論は改善のための呼びかけです。解決策は、ミームコインの楽しさと実用性を融合させたより良いトークン設計から始まるかもしれませんし、長期保有を奨励する文化的シフトから始まるかもしれません。Believeのようなプラットフォームは、ローンチ時からエクイティに近い上振れ(equity-like upside)を強調するようブランディングを調整できるでしょう。コミュニティとしては、初期状態の不信感を捨て、継続性を示すプロジェクトを支援する時です。
暗号が進化する中で、ICMは確かに次の大きな潮流になり得ます――真にインターネットネイティブな資本市場として。ただしそのためにはEdgarのような胆力ある創業者が先導する必要があります。あなたはどう思いますか?技術の問題でしょうか、それとも文化の問題、それとも両方でしょうか?下のコメントで意見を聞かせてください。そして次のムーンショットになり得るICMの動きを要チェックです。