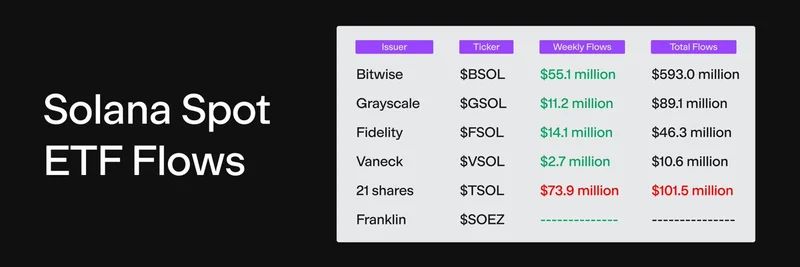In the fast-paced world of DeFi, opinions and best practices evolve quickly. A recent tweet from mst at Raydium highlights a key shift: the realization that spot market prices of wrapped assets shouldn't be the ultimate authority for triggering liquidations. This comes as a relief to early adopters who faced backlash for pushing this idea.
ラップ資産と清算を理解する
まず、分解して考えよう。ラップされた資産とは、他の暗号通貨やトークンをトークン化し、異なるブロックチェーンやプロトコルで互換性を持たせるために作られたものだ。例としては、Solana上の Liquid Staking Tokens(LSTs)である mSOL があり、これはステーキングされた SOL を表しつつ流動性を提供する。一方、USDe は Ethena の合成ドル安定通貨だ。
清算は、借り手の担保価値が一定の閾値を下回り、貸し手の資金がリスクにさらされるときにレンディングプロトコルで発生する。損失を防ぐためにプロトコルは担保を売却する。問題は:その担保をどうやって正確に評価するかだ。
従来、一部のプロトコルはスポット価格—たとえば Raydium のような DEXes 上の現在の取引価格—を参照してきた。しかし先のツイートが指摘するように、これは問題になり得る。スポット価格は変動しやすく、流動性の低いプールでは操作される可能性もあり、不当または時期尚早な清算につながる。
0xRooter と Solend の経緯
ツイートでは、Solend(現在は Save Finance にリブランド)創業者の @0xrooter のようなオペレーターにも言及している。当時、0xrooter と彼のチームはスポット価格の代わりに、オラクル価格や資産の裏付けとなる償還可能価値など、より信頼できる指標を使うことを主張していた。このアプローチは市場操作からユーザーを守ることを目的としていた。
しかし、この立場は批判も招いた。批評家はそれが「純粋な」市場主導のメカニズムから逸脱し、オラクルを介した中央集権的リスクを招く可能性があると主張した。とはいえ、様々な crypto discussions で指摘されているように、この方針は現在コミュニティ内で合意に近づきつつある。
ミームトークン愛好家にとってなぜ重要か
Meme Insider はミームトークンを中心に扱っているが、この種の DeFi の仕組みはミームが活発に流通する広いエコシステムに直接影響を与える—特に Raydium 経由でローンチされたバイラルなプロジェクトが多い Solana 上ではなおさらだ。レンディングプロトコルでミームトークンを担保にして取引や保有をしているなら、清算トリガーの仕組みを理解することがポジション維持か強制売却かの差を生む。
たとえば、ミーム関連のイールドファームに裏付けられた LST を担保に使ったとしよう。流動性が低いためにスポット価格が一時的に下落すれば、基礎となる価値が堅調であっても強制的にロスを被る可能性がある。スポット価格依存から離れることは、公平性と安定性を促進し、ミームクリエイターやトレーダーにとって DeFi をよりアクセスしやすくする。
今後の道筋
この合意の進展は DeFi の成熟を反映している。プロトコルは Pyth Network のようなオラクルとスポットデータを組み合わせたハイブリッドな評価方法を採用するケースが増えており、これはリスク管理とユーザー保護の観点で歓迎すべき動きだ。
ブロックチェーン実務者として、こうした微妙な違いを把握しておくことは現場を乗り切る助けになる。Solana 上で構築しているにせよ、ただミームを楽しんでいるにせよ、すべての価格が同等に扱われるわけではないことを忘れないでほしい。嵐を乗り越えた 0xrooter のような先駆者たちに敬意を表す—彼らの行動がより強靭な暗号の風景を切り開いている。